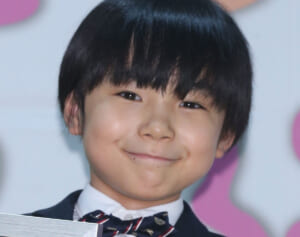■「音楽があればきっと人生が潤うはず。“音楽のバリアフリー”をテーマに活動を」
大阪府枚方市に’74年に生まれた竿下さんが、ピアノと出合ったのは5歳のときだった。
「母が、ピアノを習うと想像力や感情をつかさどる右脳の発達にいいからと、ご近所のピアノ教室に通うことに。私は鍵盤に触れた瞬間から、感情をメロディで表せるピアノが好きになった。きちんと弾けたときにもらえる“○(マル)”もうれしくて、すごいスピードで課題をこなしました」
近所のピアノ教室の先生に「こんなにピアノが好きやったら」と勧められ、小学生に上がったころ大阪音楽大学付属音楽学園(現付属音楽院)に通った。京都市立堀川高校音楽課程(現京都堀川音楽学校)に進み、大学は京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻に。大学卒業後は、全国各地で演奏を重ね、ピアニストとして活躍した竿下さんだが、どこかしっくりいかない自分がいたという。
「クラシック音楽は、裕福で品のいいお嬢さんが好きなことをやっているというイメージを多くの人が持っていました。一方、演奏家も音楽以外のことは何もできなくてもいいという風潮がありました。
音楽がなくても人は生きていけるけれど、音楽があればきっと人生が潤うはず。ちょうど『バリアフリー』という言葉が出始めたころで、社会のなかに音楽があることで音楽は社会にもっと愛されるのではと“音楽のバリアフリー”をテーマに活動を始めました」
日本におけるクラシックの世界はコンサートホールに人が集まってきて聴くのが当たり前だった。しかし、それだと音楽に興味のある人しか集まらない。そう考えていた竿下さんは、公民館や高齢者施設などに出向いて演奏を届ける活動に力を入れた。
「音楽家がいろんな場所で演奏することは、今では当たり前ですが、当初はそんな活動をするピアニストは少なかった。集まった方々に、クラシック音楽の奥深さを知ってもらい、コンサートホールまで足を運んでくれる人が増えたらいいなと」
’00年から10年間住んだ大阪府泉大津市では、そんな地道な活動が評価され、’06年に同市の「フカキ夢・ひとづくり賞」を受賞。
「副賞としていただいた賞金で、市役所に電子ピアノを寄付しました。そのピアノで月に1度、ランチタイムだけの演奏会をしました。市役所に用事があって訪れた人がふと足を止めて耳を傾けてくれる。そんな活動を続けていくうちに、音楽で町づくりができないかと思うように。音楽があふれる町づくりという次なる目標が見えてきました」
私生活では、学生時代に知り合った延日呂さん(49)と結婚。一人娘も誕生した。’10年には夫の仕事の関係で京田辺市へ――。そんな竿下さんを病魔が襲った。最初の症状は軽いせきだった。
「せきが気になるので’23年1月に病院で検査したところ肺炎ではないかと。ところが薬でもいっこうに改善しない。そこで宇治徳洲会病院(京都府宇治市)で、肺の細胞組織をとる『気管支鏡検査』をしてがんとわかりました」