
<この物語は、ある霊能力者をモチーフにして描かれたフィクションである。>
「ばあさんと一緒やなぁ。血ぃは争えんな…」
中村のおばちゃんは、小さい頃の明美を可愛がってくれた今は亡き祖母の幼馴染みだ。まだ明美が実家に居た頃は、地元で小さな電気屋さんをしていた。元々は亡くなったおじさんが始めた店で、他に競合する店も無い田舎町ではそれなりに繁盛していた。しかし時代は移り変わり、やがて大型の家電量販店がひしめくようになれば小さな店など続けていけるわけがない。おばちゃんの息子は継ぐこともできずに、町で会社勤めをしながら暮らしている。現在は商売もやめ、90歳になろうとするおばちゃんが一人で暮らしているが、週に一度は娘さんが様子を見に来るらしい。祖母とは小さい頃から仲良しで、昔からよく家に来ていた。今でも明美が戻ってくると野菜や何かを届けてくれたりする。
初七日を済ませ一息ついた頃から、誰に聞いたか一人二人と相談者が訪ねてくるようになっていた。
中村のおばちゃんは、毎日のように訪ねてきてはお茶をして帰るのだが、どうやら、おばちゃんが噂を広めている張本人のようだ。嫌な気はしない。と言うより、明美はそんな、今は亡き祖母の幼馴染みがしてくれるおせっかいが嬉しかった。そして、孫ですら怖いと思っていた祖母の在りし日の姿を面白おかしく話してくれるおばちゃんと話していると、出来ずに終わったおばあちゃん孝行の真似事をしているような錯覚を味合わせてもくれた。
老婆からの相談
それは、初七日を明日に控えた朝のこと。
「中村のおばちゃんから」
差し出された子機の向こうから、聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「明美ちゃんかえ。アンタ、わからんやろか?」
「なに? どうしたのおばちゃん」
いつもの口ぶりとは違い、電話の声に切羽詰った感じが漂っている。
「ほうよ、困っとるんよ。…じいさんにもろた指輪がのうなったんよ」
「どうしたの? おばちゃん。ちゃんとしてたの?」
「今朝はちゃんとしとったんよ。…それが無いんやがね」
どうやら中村のおばちゃんは、今朝までしていたらしい大切な指輪が無くなりパニックに陥っているようだ。
明美は受話器をテーブルに置くと、静かに目を閉じて声の向こう側へと意識を凝らせていく。
最初に浮かんできたのは、今も当時の看板が残るおばちゃんの家の屋根瓦。そこから家の中へと意識を潜り込ませていくと、丸いちゃぶ台に向かって一人でご飯を食べているおばちゃんの背中が見えてきた。
さらに意識を、お茶碗を持つ左手に移していく…。

確かに、指には見慣れた指輪がある。少しページ(?)を進めてみる。次に現れたおばちゃんは流しで食器を洗っていた。手先へと意識を移すと…指輪が無い。
また、ページを少し戻してみる。すると、何を思ったかおばちゃんが、流しに向かうその手前で指輪を外し、食器棚の一番上の引き戸を開けて仕舞う姿が見えた。
「…よく聞いて、おばちゃん。流しの横にある食器棚の一番上の引き戸を開けてみて…。そこに無い?」
「え~…。一番上の引き戸じゃて…」
おばちゃんが受話器を置き、流しに歩いていくのがわかる。ブツブツ言う声が、少しずつ遠ざかっていく。
「あった。ほんとにあったぞね。…ようわかったな、あんた。ありがとう、ありがとう」
明美が言ったとおり、指輪は引き戸の中にあったらしい。受話器を手にお辞儀でもしているのだろう、普段よりも一際高い声が微妙に上下している。
祖母の教え
「知っとるかな? ばあさんはすごいおひとやったんやで。相談に来た人の前で、こう…お祈りするやろ、そしたらもう別人になるんや。あるときはな、座ったままの恰好で一尺も跳ね上がったもんや。そらもう、この目で見ても信じられん光景じゃったわい」
その日の午後、中村のおばちゃんは失くしたはずの指輪を手に、明美の前で嬉しそうにお茶を啜っていた。
同じ光景ではないが、小柄な祖母の身体が、およそ人間とは思えない奇妙な格好で跳ね上がるのを明美自身も目にしたことがある。まだ小学生だった明美は、そんな祖母に恐怖してしばらくは眠れなくなったものだ。
「それにしてもばあさんと同じことを始めるとはなぁ。ばあさんも喜ばい」
一人暮らしは寂しいだろうし、昔語りが楽しいのだろう、中村のおばちゃんは二日に一度は現れる。
「ばあさんの口癖は『内観せえ』やったな。内観て、お寺さんにでもいかな聞けん言葉じゃけど、いっつも言いよったわい。なんでも、悩みや迷いは自分が生み出すんじゃと。ほやけん、そんな時はじっくりと自分自身を見つめ直せば答えは見つかるんじゃ言いよったわい」
また教えられた。こんな風におばちゃんは、その時々で明美が求めている、祖母が生きていれば聞いてみたかった事を抜群のタイミングで口にしてくれたりする。
見よう見真似で始めたリーディングだったが、いくら「見える」とか「聞こえる」などと言ったところで、それがいったい何を伝えようとするヴィジョンなのか…明美自身にもわからなくなることがある。そんなとき明美は、『おばあちゃんに聞きたい』と思う。東京のマンションでするよりも、「同じ所でやりよらい」と中村のおばちゃんが言う、神棚のある座敷でする方が格段にし易すかったが、それでもわからないことが多過ぎた。
言うなればそれは瞑想なのだろう。中村のおばちゃんが言うように、祖母がしていたらしい内観を実践してみると、確かにそれまでは一枚か二枚でしかなかったヴィジョンが、始まりと行方を示すように順を追って何枚も現れることがわかってきた。
最初はお風呂の中だった。
バスタブにお湯を張り、身体を沈めて意識の内側を凝らしていく…。すると、気掛かりなことに関連するヴィジョンが次から次へと現れた。そうするうちに、バスタブでよりも神棚の間で香を焚いて意識を澄ませると、より一層意識が研ぎ澄まされていくのがわかった。
そんな風にひとり試行錯誤を繰り返しながら、いつしか明美なりの内観法が出来ようとしていた。
言うまでも無くリーディングの内容は相談者によって変わるのだが、リーディングすることによって得られるヴィジョンに辿り着くまでのプロセスにはひと通りの流れがある。
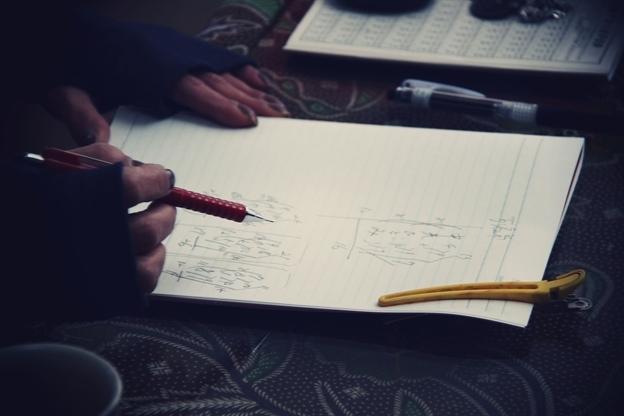
相談者は、まずリーディングシートに姓名と生年月日を記入する。明美はその間、瞑目したまま両手を広げ、相談者のチャクラの具合を診断する。それが終わると、明美は記入された姓名で画数を数えながら相談内容を口にし、おもむろに対処法なり解決策を諭していくのだ。
たいていの相談者は、画数を数えながら悩みを口にした時点で驚く。なぜならこの時点では、相談者はまだ明美に何も話していないからだ。
そんな相談者の多くが、リーディングが終わると、「どうして(私の悩みが)わかったんですか?」と口にするのだが、それには秘密があった。
明美は、相談者がシートに記入する間に、すでに相手の精神の領域に軽く触れてみているのだ。相談者がうつむき加減で記入し始めると、明美は掌を合わせて瞑目し、かつて祖母に教えられた光明真言を胸の内で唱える。
“おん あぼきゃ べいろしゃのう
まかぼだら まにはんどま
じんばら はらばりたや うん”
すると、相談者が思い患っていることが、それにまつわる姿で見えてくるのだ。
たとえば、パートナーを忌み嫌い別れたいと思いつつも子どもを授かりたいと、ともすれば矛盾するような願いを抱えた相談者からは、パートナーを口汚く罵る姿と共に嬰児を抱きしめるような相反するヴィジョンが同時に浮かんできたりする。また、職場の人間関係で悩んでいる人からは、オフィスと思しき一室で相談者が働いている背後に、陰口か何かを言い募る人たちの姿が垣間見えたりした。
それがそのまま、相談者の日常や実情を覗き見ていることもあれば、相談者自身の抱くイマジネーションが形を成している場合もある。

相談者の記憶を読み解くことであると同時に、そんな相談者が陥っている精神の領域を覗き見ることなのだろう。「精神の領域」とは言っても、明美が覗き見るそこは、相談者自身の感情に支配された、最も手前にある領域だと認識している。まずは、この感情に支配された精神の領域に触れることによって、明美は相談者を苛む現実と精神状態を知ることができた。
感情とは精神と肉体をつなぐファクターであり、相談者を支配している感情を把握することによって健康状態や社会性までをも窺い知ることができる。まずは、そんなプロセスなのだが、値踏みでもするつもりでやって来た不心得者の出鼻をくじくには最も効果的な手法でもあった。
しかし、中にはどす黒く濁った激しい怒りや、今にも崩れ落ちそうな悲しみに満たされた相談者もいて、そんな激情の襞に触れてしまうと明美自身も相当のダメージを被る。酷い時には、明美自身の精神をも侵食されそうになった。それでも明美は、より確度の高いリーディングをするには、感情に支配された精神領域を知ることが重要だと考えていた。
「おばちゃん、裏巳午って知ってる?」
先ほど帰った相談者、リーディングシートに上村静江と書いていた。京子に聞いた、一人娘を亡くした母親と同姓同名だ。亡くなった祖母や曾祖母のように、数え切れないほどの相談を受けてきたわけではないが、さっきの母親ほど哀しく苦しいリーディングは経験したことがない。
地獄を歩む母親
その日相談にきた上村静江にとって、愛娘の理沙が居ない日々など、どこまでも続く砂の山を登り続けるようなものだった。それを宗教家は、無間地獄と呼ぶ。まだ32歳の静江は、数千年に渡って人類が畏れ続けた地獄に生きていた。
どこにでもいる、当たり前の若い夫婦にできた可愛い女の子。一人娘の理沙は、特に目立つ存在ではなかったが、気立ての良い笑顔の可愛い娘だった。
不幸な事故は、そんな理沙が楽しみにしていた臨海学校で起きた。
小学校に上がって通うようになったスイミングスクールは、理沙を学年でも1~2を争う水泳自慢にしてくれた。だからこそ、年に一度、瀬戸内海に面した海水浴場で開かれる臨海学校を、理沙は特に楽しみにしていたのだ。基本的には全員参加となっている臨海学校だったが、近頃はお受験に備えての夏期講習とか健康上の問題とかで参加しない児童も少なくないが、泳ぎの上手な理沙にとっては何よりも楽しみな行事の一つだ。

臨海学校では学年別に水泳講習が開かれ、学年毎に設定したカリキュラムをクリアするに従って金・銀・銅とメダルが授与される。一年生から参加し、二年連続で金メダルを貰って喜んでいた理沙は、三回目となる今年こそは泳ぎだけじゃなく他の生徒のお世話ができた生徒に贈られるキャプテン徽章を狙っていた。おおよそキャプテン徽章を付けているのは六年生と五年生で、四年生でも付けている児童は2~3人しかいない。
理沙は、泳ぎでなら四年生にも負けない。そんな理沙が、密かに狙っているのがキャプテン徽章だ。常に教師の傍にいて、生徒を整列させたり点呼を取ったりと、授業のお手伝いをする臨海学校のエリート。この、通常のプール授業でも一目置かれるキャプテンの称号に理沙は憧れていた。
そんな水泳自慢の理沙に、学年の誰よりも泳ぎの達者な小学三年生の少女に、ほんの少しだけ油断をした教師が目を離した瞬間に、取り返しの効かない悲劇は起きてしまった。
リーディング
リーディングとは、対象の意識や無意識を読み取ると同時に、その周囲に現れる様々な意識と交感すること。近年、「スピリチュアルリーディング」という言葉が当たり前のように使われるようになったが、真印さんは「これは単なる符丁でしかありません」と話す。真印さん曰く、その対象は人間に限らない、とも。実際に、真印さんの能力は、犬、猫、樹木、さらには石などの無機物にまで及ぶ。そう、真印さんは、樹木や石に蓄積された情報(記憶・記録)にも、触れることが出来るというのだ。「まだ何も解明されておりませんが、それらが等しく有するものがあるとすれば、それは波動のようなものかもしれません。水面に揺れる波紋を見るたび、その広がりの様子に、リーディングのメカニズムを想像しています」(真印さん)。現在も、物語のヒロイン・明美のモチーフとなった能力者・真印さんは、さまざまに検証を続けているのです。
著者プロフィール
那知慧太(Keita Nachi)愛媛県松山市出身 1959年生まれ
フリーライターを経てアーティストの発掘・育成、及び音楽番組を企画・制作するなど、東京でのプロデュース活動を主とする。現在は愛媛県に在住しながら取材・執筆活動に勤しむ。『巳午』を処女作とする。








