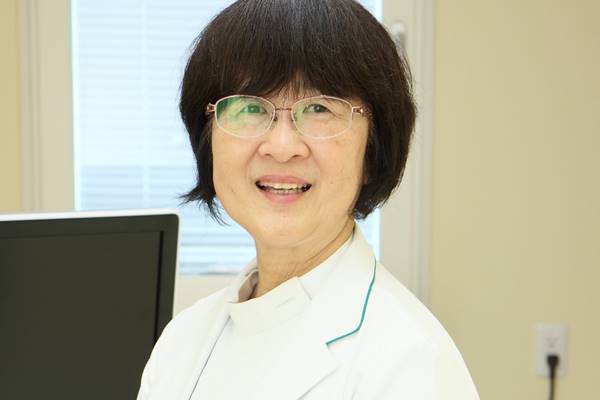「女子は減点」の医大入試もしかり、医療現場はまだまだ女性にやさしくない。改善されないのなら自分で“お手本を見せる”と、ある女性医師が立ち上がった。
「東京医科大学で受験者の得点を意図的に操作し、女子入学者数を抑制していたことは、医師を目指している女性全体にとって許しがたい不正。大学からは、出産や育児で離職、休職せざるをえない女性医師を、積極的に合格させたくないという思惑を感じます。こうした問題を解決するために不可欠なのは、出産・育児のある女性医師が働きやすい、復帰しやすい医療現場を作ることです」
そう語気を強めるのは、6月に開院した「みなみ野グリーンゲイブルズクリニック」(産婦人科)の桑江千鶴子院長(66)だ。東京都立多摩総合医療センターの産婦人科部長として、緊急帝王切開や高難度の婦人科手術でメスを握っていたが、現在は、女性医師を含む、女性全体が安心して出産・育児ができる枠組みを作ろうとチャレンジしている。
女性医師に寄り添う医療現場は少なく、出産育児を機に、キャリアを捨てざるをえなくなったというケースは少なくない。厚生労働省の、’06~’16年の調査によると、女性医師の就業率は、医師登録して12年後、つまり出産や育児の時期と重なる30代後半で、75%ほどに下がるのだ。桑江さんが続ける。
「そうした理由から、女性医師の流出を防ぐために院内に託児所を設置する施設も増えてきました。しかし、一緒に働く男性医師の意識が古いままでは、根本的な解決にはつながりません」
女性医師のニーズの高い小児科でも「女性は出産時に辞めてしまうのでダメ」と断られたり、「2年間は妊娠するな」と条件を突きつけられることもある。
医療現場で求められるのは、24時間365日、滅私奉公で働ける医師。出産・育児は敬遠される。女性医師の割合もOECD加盟国の平均は46.5%だが、日本は20.3%(’17年)で最下位だ。
桑江さんが自らクリニックを立ち上げ、女性医師の働き方の改善を模索するのは自身も「いつ辞めようか」と考え続けてきたからだ。信州大学医学部を卒業した’77年ごろを振り返る。
「入学した100人のうち女性は4人。指導する先輩医師からは『男のほうが脳が重いから優秀』と言われ、メスも握らせてくれなかった。多くの女性医師が、当直や急患のある外科系では受け入れてもらえないだろうと最初から諦め、比較的時間に余裕が作れる眼科や皮膚科などを選びます。女性は選択の幅が狭いんですね」
卒業後、すぐに高校教師の秀夫さん(66)と結ばれる。彼女が出した結婚の条件は「子どもは産まない」ということだった。
「『いや、ちょっと待ってよ』と。ボクは子どもが好きだから、欲しかったんです。だから妻には『ボクが育てるから産んでほしい』とお願いしたんですよ」(秀夫さん)
’80年に長女・七生さん(38)を出産。その後に始まった産婦人科医の仕事は、多忙を極めた。
「娘が2歳のときに勤めていた病院は、月の分娩が120~180件もありました。保育園に迎えにいくのはいつも最後。当時、私は赤い車に乗っていたので、娘は窓の外を見ながらずっと『赤いブーブ、赤いブーブ』と言っていたそうです。保育園の先生からそれを聞いて、“寂しい思いをさせてしまっているな”と涙が出ました」
だが、立ち止まってはいられなかった。’85年に長男を出産したときも、産後2カ月で職場復帰した。
「トイレで母乳を搾っては捨てていました。せめて5カ月くらいは母乳を与えたかった……。家族旅行も、急患が入れば私だけ途中で切り上げたり、娘の誕生日ではケーキのロウソクの火を吹き消す前に病院に舞い戻ったり」
もっと子どものそばにいたい、辞めたいと何度も思った。そんなとき秀夫さんはこう言って励ました。
「本当にそれでいいのか? もし子どもが大きくなって“私のためにお母さんが好きな仕事を辞めたんだ”と思ったら、イヤだろう」
夫や夫の両親、実家の母親のサポートを得てキャリアを積み、’02年から退職する’12年まで、多摩総合医療センターの産婦人科部長を務めることができた。
「私はスーパーウーマンではなくて、迷いながらも、家族のサポートがあって“なんとか切り抜けられた”のだと思っています。そもそも“専業主婦”は高度経済成長期に生まれたもので、それまでは農業も酪農も漁業も女性は働き、育児は親戚や近所などが助け合っていた。つまり、子育ては1対1で部屋に閉じこもってするものじゃないんです」
桑江さんはかつての自分の姿を思い出す。鉄筋コンクリートのマンションの一室に子どもの泣き声が響き渡っていたとき、思わず虐待しそうになったのだ。
「そのとき母が姿を現してわれに返ったのを覚えています……。都立病院を退職してからは、非常勤医師としてクリニックなどで産後うつのお母さんの治療にあたっていたんですが、いま“医師であり母である私”ができることは何かと考えるようになって、新しい病院を作ろうと決意しました」
3人の子どもとクリニックを訪れた娘の七生さんに、“母として”の桑江さんについて尋ねてみた。
「母はいつも忙しくて、私は父と一緒の思い出ばかり。でも、育児しながらでも女性が手に職を持って働くことの素晴らしさを学びました」
女性医師たちを導く“母”として、桑江さんの挑戦は続く――。