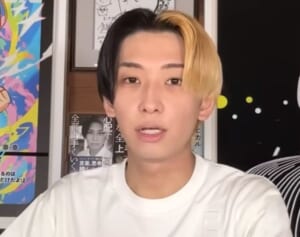■認知症を公表後、仕事は激減。見かねた旧友たちが“最後の展覧会”を計画
わたしは、本誌で連載していた「蛭子能収の人生相談」の担当記者。月1回、蛭子さんに話を聞いては記事にまとめていた。
蛭子さんとの最初の出会いは20年前。先妻に先立たれ、孤独に耐えられないと語っていた蛭子さんに「誌上お見合い」の企画を持ち掛けたのがきっかけ。蛭子さんはそのお見合いで今の妻である悠加さん(57)と巡り合った。初デートを演出したわたしは“愛のキューピッド”気取りだったが、その後、連載の打ち合わせで蛭子さんと会ったときには、わたしのことをすっかり忘れていた。
連載の人生相談は蛭子さんの“ゆるくて鈍い”回答がさえた。
たとえば、心通わせる愛猫を失ったあとのペットロスが怖い、という読者に、蛭子さんは、自ら猫を飼っていたことを明かしながらも、
「動物と人は、気持ちが通じ合いません。通じると思っているのは人間の思い込みですよ」
と、バッサリ切りつつ、死んだ猫の墓参りには毎年行っていることを付け加えた。
蛭子さんは、’14年に認知症の一歩手前である「軽度認知障害」と診断された。取材でも人の名前を忘れたり前日のロケのことを覚えていなかったりと兆候はあった。しかし、興味がないことに無関心な蛭子さんの“味”だと思っていた。
’20年7月、蛭子さんは、アルツハイマー病とレビー小体型認知症を併発していることを公にした。
「ボケても、仕事したい」
公表後にこう話していた蛭子さん。コロナ禍と重なり直接会う機会は減ったが連載は続いた。
ところが症状は思いのほか進行した。自分について語ることはできるが、人の悩みに答えるような言葉は出てこなくなった。
「今こそ蛭子さんに絵を描いてもらって、展覧会を開催できたらと思っているんです」
’21年秋、連載の担当編集者がこう切り出した。サブカルチャー好きの編集者は、タレントよりも漫画家としての蛭子さんのファン。認知症を公表後、テレビの仕事が激減した蛭子さんに、絵の仕事をしてもらおうという提案だった。
認知症をなめていると思った。
じつは、わたしの母も認知症だ。5年前に80歳直前でアルツハイマー型認知症と診断された。朗らかだった母から、昼夜問わず被害妄想にかられて「財布が盗まれた」「誰かが家にいる」と連絡が入った。読書が趣味だったが集中力がなくなり、本を手にすることもなくなった。母と接するとき、わたしの顔つきは、いつも怒りをあらわにするか無表情だった。
蛭子さんに母の姿を重ね、絵を描くことは難しいと考えていた。
それでも展覧会の計画は、蛭子さんの友人で特殊漫画家の根本敬さん(65)のサポートもあり実現に向けて動き始めた。
根本さんが語る。
「認知症を公表したあとに蛭子さんから“絵を描きたい”と電話があったんです。蛭子さんの作品に衝撃を受けて漫画家になった僕は蛭子さんに絵の世界に戻ってきてほしかった。だから『協力するよ』と返したら『持つべきものは友やね』と。それまで蛭子さんは人に僕を紹介するとき“オレのことをおもしろおかしく書いて食っている人”と平気で言う人。蛭子さんから友という言葉が出てビックリ。
蛭子さんは絵を描くスピードがものすごく速いから、展覧会はできるなと思っていました」
根本さんが知り合いの画廊と話をつけて展覧会場と開催日が確定した。あとは蛭子さんが“やる気”を出すだけだが……、それこそが最大の問題だった。