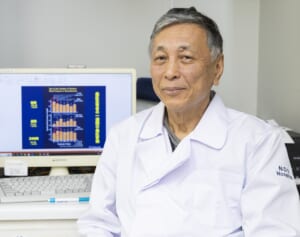「治療している病院から『これ以上やれることはない』と言われた患者さんが、医療連携室を通して私のところに来られます。その段階で、余命をはっきりお伝えします。1カ月、よくて3カ月などとね。中にはまだあきらめないという人もいますが、ここでは治す治療はない。痛みを和らげる治療のみです」
こう語るのは、在宅医療の第一人者で、医療法人社団パリアン・クリニック川越(東京都墨田区)の川越厚院長。末期がんの患者に、自宅で最期を迎える支援をする「在宅ホスピス」の取り組みを25年以上前から実践し、開業してからは2,000人以上を患者の自宅で看取ってきた。
在宅で看取りをするなら、家族は仕事を辞めてつきっきりで看護をしなければならないと不安を抱く人も多い。だが、川越先生のクリニックでは患者の1割がひとり暮らしだ。
「夫婦のどちらかが他界して、ひとりで住んでいる人が最期を迎えても、離れて暮らすお子さんたちが親御さんをつきっきりでみる必要はありません。在宅ホスピスでは、医師、訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャー、ヘルパー、ボランティアがチームを組んでケアをします。そして、誰かが1日最低1回は自宅を訪問しますし、緊急時にはすぐに駆けつけられるよう、医師と看護師が24時間体制で待機しています。他人が家の出入りをすることに理解をしてくだされば、お子さんたちが離れて暮らしていても看取ることができますよ」
「在宅死」を選択してから来院するのは10人に1人ほど。ほとんどの人は混乱の中、もがきながら決断するという。悩みも「まだできる治療があるのではないか」「治療費がかかりすぎてもうお金がない」など、病院から自宅に戻る不安はさまざまだ。川越先生はこう語る。
「いちばんお伝えしたいのは、末期の場合は『お迎え』が来るまでの時間がとても短いということです。つまり、そんなに大きなお金はかからない。『先が短いことを念頭に置いて、これからの生活設計を立てましょう』と伝えています」
治療方針をめぐって家族の中で意見の対立を起こさないためにも、元気なうちに「どんな最期を迎えたいか」を聞いておき、穏やかに過ごす看取りプランを立てておこう。
「がんの患者さんは最期が近づくまでお元気な方が多い。痛みを和らげる治療を施せば、やりたいことが最期までできます。死期がわかっていても前向きに生きる。ご本人も家族も不安が解消され、のびのびと過ごされている。それがとても大事なことだと思います」