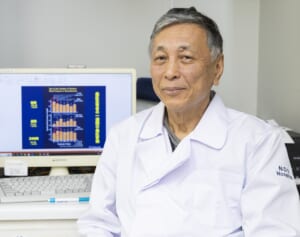あなた自身が、もしくは家族が、がんで“余命宣告”を受ける日が来るかもしれない。目の前に死を突きつけられたとき、冷静ではいられないだろう。しかし“残りの時間”を知ることで、新しく開ける人生もあるという。
「“余命”という言葉は“余った命”と感じられて、好きじゃないです。ボク自身は、人生の最後、懸命に生きるために残された貴重な時間だと思いますから」
そう語るのは、金沢赤十字病院の副院長を務める、医師の西村元一さん(58)だ。’83年に金沢大学医学部を卒業して以来、消化器外科畑を歩んできた。専門は大腸がん。当然、日常的にがん患者とも接してきた。
「患者さんにも人生があり、残された命を知ることで、家族との時間を大切に過ごしたり、先送りにしていたことを終わらせることができます。だから、医師として予後(余命)は伝えるようにしていました」
患者の大部分は簡単に死を受容できないというが、それでも人生の終着点に向けて、歩んでいたという。
「あきらめに近い心境かもしれません。正直、ボクも死から目を背けている部分があります。それでもボクには長い命が残されていないので、できないことはすっぱりと切り捨て、本当に自分にしかできないこと、やりたいことを優先するしかありません」
病室のベッドで、点滴用の針が差し込まれた腕をなでながら冷静に語る。じつは西村さんも「何の治療もしなければ余命半年」と宣告された胃がん患者なのだ。自らの体験をまとめた『余命半年、僕はこうして乗り越えた!』(ブックマン社)を出版すると、全国から講演依頼が。
「北は北海道、南は九州に至るまで。そのとき、ずっと家内と一緒でした。今もほとんどの時間を妻と過ごし、元看護師の妻がボクの専属看護師兼秘書兼運転手をこなしてくれています。結婚以来、初めて家内と一緒にいられる時間があるのも、キャンサーギフト(がんが与えてくれる贈り物)なのかもしれません」
妻のサポートを受けながら、医師人生の集大成として実現すべき夢に向き合えたことも、西村さんにとっては“ギフト”だといえるかもしれない。
「医師として生きてきて、やはり自分のことだけでなく、ほかの誰かの役に立ちたいと考えました。そこで思い至ったのが、金沢に“マギーズセンター”のような施設を設立することです」
イギリス発祥の“マギーズセンター”とは、がん患者や家族などが受付けも予約もなしで、気が向いたときに気軽に集まって話し合える病院外サロンのこと。
「がんが発覚する5年ほど前にその存在を知って、金沢にも似たものを作ろうと専門家を招いてシンポジウムを開催するなどしていたんです。しかし完全なボランティアなので、運営するとなると寄付に頼るしかない。資金不足で計画は足踏み状態。年に1日だけ“マギーの日”を設けるにとどまり、事実上、計画は中断していました」
だが、西村さんががんになったことで、計画が一気に動きだした。
「ボク自身が、家内にも主治医にも言えないことや、がん患者しかわからない不安を、同じ立場の人と分かち合いたかったんです。そうした思いを多くの人が受け止めてくれたんですね。これまでお付き合いのあった医療機器メーカーが場所を提供し、かつての患者さん、活動に理解してくれた多くの人が寄付をしてくれて……。何年も止まっていた計画が、たった9カ月で実現したんです」
’16年12月に「元ちゃんハウス」としてオープン。西村さんは設立者であり、利用者でもある。
「がんになったからこそ実現できた夢です。たとえ厳しい予後であっても、そこから新たな人生設計だって作れるはずです」