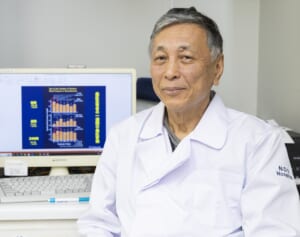高齢者の5人に1人が認知症になる、という時代も近い。将来の認知症への不安と、どう付き合えばよいのか――。
「父の日記には『電車を乗り間違えた』『講演の途中で話すことがわからなくなった』といった記述がだんだんと増えていきました。認知症の専門医である自分が、認知症かもしれない……という恐怖や心配は、父の心にあったと思います」
そう語るのは、認知症専門医の長谷川和夫さん(92)を父に持つ、南高まりさん(59)。
長谷川さんは、聖マリアンナ医科大学名誉教授で、認知症研究の第一人者。当たり前のように使われていた「痴呆症」という呼称を改めることに尽力し、認知症診断の物差しとなる「長谷川式簡易知能評価スケール」を開発した人物だ。
そんな長谷川さんが『僕も認知症なんです』と明かし、世間を驚かせたのは’17年10月のこと。以後も長谷川さんは、進行していく症状を受け入れながら、認知症にまつわるさまざまな情報を発信し続けている。
長谷川さんの活動をサポートしている長女のまりさんは、“父の記憶に残せるように”と、『父と娘の認知症日記』(中央法規出版)を今年1月に出版。長谷川さんの日記や写真を基に、60年の歩みをまりさんの視点で綴っている。
長谷川さんが認知症になって気づいたことは、“認知症になったからといって、すべてがわからなくなってしまうわけではない。症状やメンタリティには波がある”ということ。
「症状が進んでいくことへの苦しみや葛藤はやはりあったようです。『きついなぁ』と口にすることもありました。以前、父が外来で診ていたアルツハイマー病の牧師さんのことを話してくれたことがあって。その方はよくオルガンを演奏しておられたのですが、亡くなったあとに『僕にはメロディーがない、和音がない。共鳴がない。帰ってきてくれ、僕の心よ、全ての思いの源よ。』(※一部抜粋)と書かれた五線紙が見つかったのです」
闘病中の苦しみと絶望がにじみ出た牧師さんのメモを見た長谷川さんは、「僕は患者さんの脳の状態を研究してきたけれど、本人の心の中を見たのはこれが初めて」と涙があふれたそうだ。
ケアする側にもされる側にとっても必要なのは、安易に「声をかけあう」のではなく、「心を支えあう」関係性を築くこと。そう長谷川さんが説くのは、自身が地域のつながりに助けられたからだ。
「父は認知症になる以前から、近所の『カムイ』という珈琲店に行くのが楽しみで、私もよく一緒に行きました。店主は父のことをよく理解してくださっているので、ひとりでも安心してくつろげる場所だそうなんです。そして40年以上父が通ってきた理髪店の『トリム』さんは、父がひとりで行けなくなると送迎までしてくださって。認知症になってから『支えてください』とお願いするよりも、当たり前の生活ができているころからつながりをつくっておくということが大事なんだと思います」
サポートしてもらえる絆さえあれば、認知症であっても地域で生活できることを証明した長谷川さん。しかし、その環境づくりこそが大きな課題でもある。
「父はいつも、『人はみんな生きてきた道のりがあって、その人しか持っていない関わりがある。だから、その関わりを大事にして絆をつくってほしい』と言っています」
さまざまな人に支えられながら、穏やかな日々を過ごしていた長谷川さんだが、昨夏に体調を崩し、妻・瑞子さんとともに老人ホームに入居。体調は落ち着いているというが、コロナ禍のため、面会が許されるのは15分のみだ。
「父はおそらく、ちょっと前のことや、先の予定なども把握しづらくなってきていて。『僕が今持っている物は時間だけ。だから“今”を一生懸命生きるんだよ』と口にしています。だから私は会ったときに必ず、『今やりたいことはある?』といったような、明るい話題を振るようにしていますね」
「女性自身」2021年4月6日号 掲載