健康
1076 ~1100件/2460件
-

江原啓之さん、コロナ禍を語る「これは人間の醜さ暴く“あぶり絵”」
2020/06/20 06:00「『国破れて山河あり』という言葉がありますが、このコロナ禍にあって、長年汚染されていたベネチア運河の水が今、きれいに澄み渡っているそうです。人々が自粛生活を送ったことでCO2が削減され、地球温暖化に歯止めがかかるなど、図らずも自然が美しさを取り戻しているともいわれます。今回のパンデミックは、人間の予想を超えた影響をもたらしているということでしょう」昨年から「令和2年は“破綻と崩壊の年”になる」と本 -

無自覚に“かくれ脱水”…高齢者は「マスク熱中症」に細心注意
2020/06/15 11:00「毎年、夏本番の暑さを迎える7月以降は、誰もが熱中症に対する警戒意識を持ちます。しかし、5〜6月の時期も、熱中症で救急搬送される人が年々増え続けているんです。気温が一気に上昇したときに発生しやすく、いまの時期から注意をしておくべきでしょう」こう警鐘を鳴らすのは、堺市立総合医療センター救命救急科の医師で、熱中症予防啓発ネットワーク代表の犬飼公一さん。大量に発汗し体内の水分や塩分が失われ、めまいや頭痛 -

冷房はケチらずつける!「室内でも熱中症対策を」と専門医
2020/06/15 11:00「コロナ禍のいまだからこそ、対策が重要」と熱中症の専門家は警鐘を鳴らす。熱中症は、予防さえすれば“確実に防げる病気”。だからこそ、万全の対策をしたいーー。「毎年、夏本番の暑さを迎える7月以降は、誰もが熱中症に対する警戒意識を持ちます。しかし、5〜6月の時期も、熱中症で救急搬送される人が年々増え続けているんです。気温が一気に上昇したときに発生しやすく、いまの時期から注意をしておくべきでしょう」こう警 -

1日2〜3個の卵が認知症予防になるワケ、71歳医師が解説
2020/06/15 06:00「今、日本に認知症の人は460万人以上、予備群である軽度認知症(MCI)までを含めると860万人以上いるといわれています。これから自粛生活が徐々に解除されても、外出を控える生活はまだ続くでしょう。そうなると、新たな発症者や、重症化する人が想像を超えて増えるのではないか、ということを危惧しています」と警鐘を鳴らすのは、諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田實さん。巣ごもり生活が長く続き、人と会わない・接触 -

71歳の現役医師語る「認知症さける食習慣」青魚は週2回
2020/06/15 06:00「今、日本に認知症の人は460万人以上、予備群である軽度認知症(MCI)までを含めると860万人以上いるといわれています。これから自粛生活が徐々に解除されても、外出を控える生活はまだ続くでしょう。そうなると、新たな発症者や、重症化する人が想像を超えて増えるのではないか、ということを危惧しています」と警鐘を鳴らすのは、諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田實さん。巣ごもり生活が長く続き、人と会わない・接触 -

腸の活性化のため医師が考案、1日5分「腸ひねりストレッチ」
2020/06/11 11:00例年とは違う生活サイクルが続くことで、気づかぬうちに腸内環境を悪化させている人が多いという。蓄積したダメージをケアするために、早めに対処しておこうーー。新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛生活が長引いたことで、腸の不調を訴える人が増えているという。便秘外来がある松生クリニック(東京都立川市)の松生恒夫院長は次のように話す。「在宅時間が長くなったことによって、腸に負担をかけている原因のひとつは運動不 -

「在宅生活で腸に負担が」と医師警告“巣ごもり便秘”に注意
2020/06/11 11:00新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛生活が長引いたことで、腸の不調を訴える人が増えているという。便秘外来がある松生クリニック(東京都立川市)の松生恒夫院長は次のように話す。「在宅時間が長くなったことによって、腸に負担をかけている原因のひとつは運動不足です。不要不急の外出を控えることで活動量が低下すると、同時に腸の動きも鈍くなります。すると、体の外に排出すべき便が腸内にたまり、便秘になります。これは -

「受動喫煙回避が重症化防ぐカギに」医師語る今後のコロナ対策
2020/06/04 15:50「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

「WITHコロナ」の時代に向けて実践したい「呼吸筋ストレッチ」
2020/06/04 15:50「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

肺炎の重症化を防ぐため「気道クリアランスの維持を」を医師
2020/06/04 11:00「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

コロナ重症化防ぐため医師がすすめる「2週間以上のヨーグルト」
2020/06/04 11:00「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

コロナ重症化のカギを握る「自然免疫」「獲得免疫」の正体
2020/06/04 06:00「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

今後のコロナ対策も「自分も感染するという覚悟を」と医師
2020/06/04 06:00「収束のための1カ月」と安倍首相が語った5月が終わり、ついに、東京を含むすべての都道府県で緊急事態宣言が解除された「新型コロナウイルス」。5月7日にはエボラ出血熱の治療薬だった「レムデシビル」が新型コロナウイルスの治療薬として国内初の薬事承認を受け、中旬からは医療機関での使用が認められた。また、新型インフルエンザの治療薬として開発された「アビガン」も承認こそ遅れているものの、その存在は早くから注目 -

心理学科教授「新型コロナで怖い夢を見る人が増えている理由」
2020/05/25 06:00「悪夢は、本人が対処できないストレスフルな出来事があると多く生じるものです。長期化する新型コロナウイルスの影響によって、心理的ストレスを感じている人がたくさんいるので、悪夢を見る人も増えていると思います」こう語るのは、これまで国内外3,000人以上のサンプルを収集し、統計学の視点で夢の研究を続けている東洋大学社会学部社会心理学科教授の松田英子さん。感染者数や死者数の多いアメリカ、フランス、イタリア -

新型コロナが不安でも…心理学の専門家教える「悪夢の撃退法」
2020/05/25 06:00最近、悪夢を見ることが増えていませんか? おそらくウイルスに対する恐怖、自粛生活によるストレスや不安からくるもので、あなただけではないのです。必要以上に恐れず、さらに3ステップ安眠術を試してみましょうーー。「悪夢は、本人が対処できないストレスフルな出来事があると多く生じるものです。長期化する新型コロナウイルスの影響によって、心理的ストレスを感じている人がたくさんいるので、悪夢を見る人も増えていると -

「すぐ批判したくなる」自粛生活中の精神ケアにベストな方法
2020/05/15 06:00政府が緊急事態宣言の延長を発表したことにより、自宅で過ごす時間の長い日々はまだしばらく続くことに。在宅中はついつい自分を甘やかしてしまうという人も少なくないだろう。しかし、そんな悪習慣が体に及ぼす悪影響について、疲労外来ドクターの工藤孝文先生は警鐘を鳴らす。「海外では、感染予防のための外出禁止や隔離の長期化により、うつや不安障害などの症状を発症している人が急増しているという報告が次々と出ています。 -

巣ごもり生活ではPC操作の姿勢に注意、30分に一度は深呼吸を
2020/05/15 06:00政府が緊急事態宣言の延長を発表したことにより、自宅で過ごす時間の長い日々はまだしばらく続くことに。在宅中はついつい自分を甘やかしてしまうという人も少なくないだろう。しかし、そんな悪習慣が体に及ぼす悪影響について、疲労外来ドクターの工藤孝文先生は警鐘を鳴らす。「海外では、感染予防のための外出禁止や隔離の長期化により、うつや不安障害などの症状を発症している人が急増しているという報告が次々と出ています。 -

自粛中“過度の飲酒”に「うつ病招くおそれ」と医師が警鐘
2020/05/15 06:00政府が緊急事態宣言の延長を発表したことにより、自宅で過ごす時間の長い日々はまだしばらく続くことに。在宅中はついつい自分を甘やかしてしまうという人も少なくないだろう。しかし、そんな悪習慣が体に及ぼす悪影響について、疲労外来ドクターの工藤孝文先生は警鐘を鳴らす。「海外では、感染予防のための外出禁止や隔離の長期化により、うつや不安障害などの症状を発症している人が急増しているという報告が次々と出ています。 -

唾液検査でわかる口内細菌に驚愕!改善法を歯科医が伝授
2020/05/08 06:00「自分の口の中の細菌画像を見て、こんなに! と驚かれる患者さんがほとんどですね」こう話すのは、歯科医師の前島美佳先生。しかし、今回紹介する「唾液検査」、聞いてもピンとこない人が多いのではないだろうか。「成人の口の中には約500種類の細菌が存在し、よく歯をみがけている人で1,000億〜2,000億個、多い人では1兆個といわれています。この細菌が虫歯や歯周病だけでなく、感染症の原因にもなるので、自分の -

虫歯&歯周病リスクを調べる「最新唾液検査」歯科医が紹介
2020/05/08 06:00「成人の口の中には約500種類の細菌が存在し、よく歯をみがけている人で1,000億〜2,000億個、多い人では1兆個といわれています。この細菌が虫歯や歯周病だけでなく、感染症の原因にもなるので、自分の口腔内の状態を科学的に知る手段として、唾液を調べることは非常に有効なんです」こう話すのは、歯科医師の前島美佳先生。前島先生のクリニックでは、4年前から「唾液検査」を本格導入。すべての患者を対象に実施し -

感染リスク抑制も 歯科衛生士教える「1回1分の正しい舌みがき」
2020/05/07 06:00毎日歯みがきはしているけれど、舌もきちんとケアしているという人は多くない。けれども、じつは舌の掃除こそ、感染症を予防するためのカギなのだーー。新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、少しでも感染予防につながる方法を求めている人は多いだろう。歯科衛生士として50年以上のキャリアを持つ、「歯科衛生士事務所ピュアとやま」の精田紀代美代表は「舌をみがくことが感染症の予防にも有効だ」と話す。精田さんが舌の掃 -
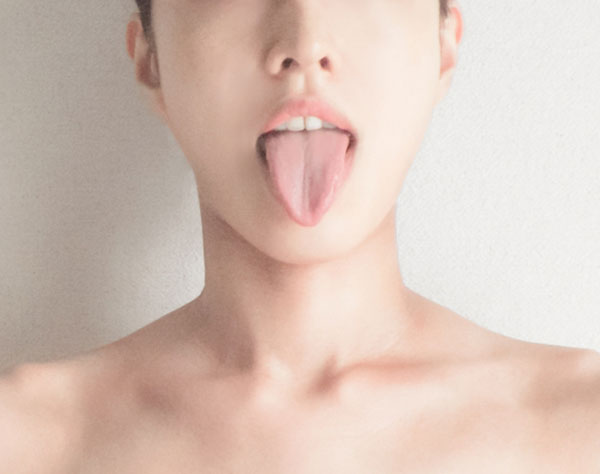
不健康な人ほど汚れが!歯科衛生士伝授「舌が汚れやすい人の特徴」
2020/05/07 06:00新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、少しでも感染予防につながる方法を求めている人は多いだろう。歯科衛生士として50年以上のキャリアを持つ、「歯科衛生士事務所ピュアとやま」の精田紀代美代表は「舌をみがくことが感染症の予防にも有効だ」と話す。精田さんが舌の掃除に着目するようになったきっかけは、10年ほど前に介護施設で口腔ケアの研修をするようになったとき。高齢者の口腔を見て驚いたという。「てっきり歯 -

医学博士警告する「スマホ認知症」30〜60代でも物忘れ多発
2020/05/06 06:00「暇さえあればスマホを触り、“写メ”をメモ代わりにしたり、出かけるときに地図アプリを使うなど、スマホに頼る生活を送っていませんか? こうした行為が、もの忘れや精神的な落ち込みなど認知症に似た症状を招いています」そう話すのは、脳神経外科医でおくむらメモリークリニック院長の奥村歩先生。外出自粛の巣ごもり中、日に何度もネットニュースを確認するなど、スマホを触る時間が長くなってはいないだろうか。奥村先生の -

自宅酒で予備軍1千万人に迫る アルコール依存症急増の懸念
2020/05/06 06:004月7日に発令された緊急事態宣言が、5月31日まで延長することが発表された。依然として世間は自粛ムード一色。そんななかで、アルコール依存症の増加が危惧される。「日本には、およそ1,000万人の“プレアルコホリック”の方、つまりはアルコール依存症の予備軍がいるとされています」アルコール依存症を含め様々な依存症問題に詳しい、大船榎本クリニック精神保健福祉部長(精神保健福祉士・社会福祉士)の斉藤章佳氏は -

女性が陥りやすい「スマホ認知症」“すぐググる”はNG習慣
2020/05/06 06:00ただでさえスマホに依存しがちなのに、巣ごもり生活が続くいま、“スマホ認知症”のリスクが忍び寄っているという。年齢層は、認知症には早い30代から中高年。特に、家事に多忙な女性は要注意だーー。「暇さえあればスマホを触り、“写メ”をメモ代わりにしたり、出かけるときに地図アプリを使うなど、スマホに頼る生活を送っていませんか? こうした行為が、もの忘れや精神的な落ち込みなど認知症に似た症状を招いています」そ

