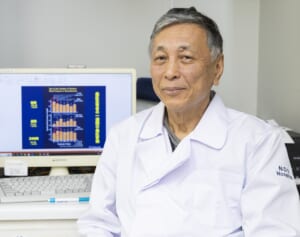■世間知らずのお嬢さんと酒飲みの鉄工職人 夫婦の連携で念願の第1号機が完成
北九州市の戸畑区で暮らし始めた利子さんは、まず小さな工場を構えて、自動車部品などの注文を受けるようになる。同時に、ポン菓子機の開発に一緒に取り組んでくれる職人を探し始めるが、そこで出会ったのが、のちに夫となる文夫さんだった。
「主人との生活? 楽しかったし、大変やったね(笑)。というのも、主人は鉄加工の腕はピカイチやったけど、酒飲みで苦労したから」
10歳年上の文夫さんは、根っからの職人肌だった。
「父は実は再婚で、4人の子供もおったそうですが、母は知らずに結婚したみたいです。仕事一筋の変わり者で、工場の徹夜作業に夢中になった挙げ句、ダライ粉(鉄くず)の上で平気で寝てるような人でした」(真貴子さん)
いとはんの利子さんと、職人かたぎの文夫さん。一見、相反する組み合わせに見える夫婦の見事な連携ぶりについて語るのは、長男の文明さん(77)。
「当時の職人さんは、うちの親父だけでなく、誰もが人見知り。口ベタではけ口は酒くらい。ですから、腕はいいがしゃべりは苦手な父が現場を担って、代わりに、ふだんの職人さんたちの世話や、営業や金策を、人当たりのいい母がやってました。終戦前後の混乱した世で、海千山千の人でひしめいていた北九州でのことですから、営業でもさまざまな障壁があったはず。ですが、母はお嬢さん育ちだったからこそ、周囲を気にせずに、理想に向かって突き進むことができたんじゃないでしょうか」(文明さん)
まさに夫婦の二人三脚で、八幡製鐡などの下請け仕事をこなしながら、開発が進んでいく。もともとポン菓子機自体は欧州などにあったが、そこに画期的な改良を施したのが吉村さん夫婦だった。
「『鋳物から鉄への軽量化』『燃料を薪からプロパンガスに』『地べたに置いていた機械に脚をつけた』この3つの改良によって、機械が安定して、容易に移動もできるようになりました。小型トラックに積んでの営業も可能に。まさに日本が得意とする、既製のものに手を加えてより便利で高品質にするという技術でした」(文明さん)
こうした日本人ならではの器用さや工夫が、ほかの分野同様に戦後の経済復興を支えていったのだ。そして終戦の年の’45年夏、悲願の吉村式ポン菓子機の第1号機が完成、特許も取得した。
「子供だけでなくまわりの大人たちも、『ほんとに、まだ子供みたいなあんたが、この機械を作ったのかい』と驚きながら、私の頭を何度もなでてくれたの」
このときの喜びと感動を、利子さんは生涯忘れない。
「ただただ、よかったという気持ち。これで子供たちを腹いっぱいにしてあげられる、と。こっそり一人で泣いたんよ。もう、うれしゅうて、うれしゅうて……」
(取材・文:堀ノ内雅一)
【後編】夫を失った後も、子育てしながら寝ずに働いて―― 子供たちのお腹と夢を膨らす「ポン菓子」広めた100歳が伝える“平和への思い”へ続く
画像ページ >【写真あり】耳も遠く忘れっぽくなったが、ポン菓子の話になると身ぶり手ぶりを交え、飢えた子らへの思いを語り続ける利子さん(他4枚)