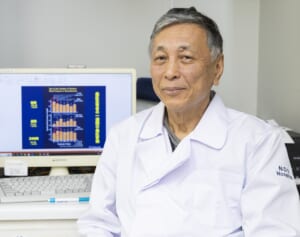■「この子らをどうにか飢えから救いたい」。鉄を求め、風呂敷包みひとつで北九州へ
「はい。私が、いとはん! 大正の最後の年の生まれ」
ちゃめっけにあふれた童女のような笑みとともに、幼い日々を語り始めた利子さん。その言葉のとおり、彼女は1926年(大正15年)1月11日、大阪府八尾市の大地主の橘家に、3人きょうだいの次女として生まれた。
「うちは蔵が4つあって、手伝いの“おとこし(男衆)”と“おなごし(女衆)”も大勢おって、大事に大事に育てられました。でも、父は二号さん(愛人)がおって家には寄りつかず、やがて両親は離婚。お金には困らなくても、寂しい思いをしたねえ」
母に代わってきょうだいの世話をしたのが祖母で、その教えが利子さんの人生観を作っていく。
「『人にはやさしく』と、ことあるごとに言われて育ちました」
大阪府女子専門学校を経て、18歳で国民学校の代用教員に。赴任した学校は陸軍の飛行場にも近く、太平洋戦争の末期には、教え子をかばってB29の落とす焼夷弾から逃げ回ったことも。
しかし、それ以上に深刻な問題があった。
「食糧難でどの子の手足も痩せ細り、おまけに燃料不足でアワやヒエなどを生煮えで食べるから、おなかをこわす子が多かった。先生になって最初の仕事は、新聞紙をちぎって手でもんでやわらかくすること。おなかをこわして授業中に便所に駆け込む生徒に、それを渡すの。もちろんトイレットペーパーなんてまだない時代やったからね。弁当を持ってこられる生徒も、60人いた子供たちのなかで、わずか10人くらいだけ。日に3件もの弁当泥棒騒動が起きることもあった」
当時の話をよく聞かされたという真貴子さんが、隣で補足する。
「母は、先生といっても当時まだ18歳ですから、教え子との年も10歳くらいしか違わなかった。だから、子供たちのひもじさやつらさも、誰よりひしひしと感じたのだと思います」
そして、利子さんは決心する。
「この子らを、どうにかして飢えから救いたい、そう思いました。穀物なら膨らませられるはずと考えて、まずは図書館で文献をあさり始めたり、知り合いの大学教授を頼って設計図も自分で描いたり」
その行動力や知識には非常に驚かされるばかりだ。
「女学校では物理や化学を専攻していたので、穀物を膨張させる仕組みは理解しとったからね」
なるほど、利子さんは、わが国のリケジョのさきがけだったようだ。大まかな設計図も完成し、次はその製造機械を具体的に形にしていく段階となったが、大きな壁にぶち当たる。肝心の材料の“鉄”がないのだ。当時、民間の金属類は、兵器製造などのために軍に徴発されていたためだ。
そんなとき、くだんの大学教授から「鉄の町・北九州なら材料があるのでは」と聞かされた利子さんは迷うことなく、製鉄会社や鉄工所などが集まっていた北九州行きを決意する。
しかし、周囲は当然、「苦労知らずで育ったいとはん(お嬢さん)が、あんな気性の荒い、大酒飲みばかりの土地へ行くなんて」と猛反対した。だが、利子さんの決意は固かった。当時の思いをこう語る。
「不思議に怖いとは思わなかったよ。それはな、私が飢えた子供たちのためにポン菓子機を作るんだ、私がなんとかせにゃいかん、しちゃるんだという、たしかな目的があったから」
1944年の夏。体ひとつ、風呂敷包みひとつで夜汽車に乗り込んだとき、利子さん、まだ18歳。それは何不自由ない“いとはん”としての生活との決別でもあった。