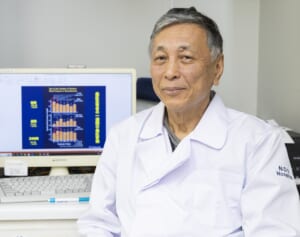かつて鉄の町として栄えた北九州に、戦争の記憶を継承する100歳がいる。吉村利子さんだ。とにかく、食べ物がなかった。燃料もなく、機械を作る鉄も足りなかった。それでも懸命に突き進む彼女の情熱は、鉄工職人を突き動かし、やがて全国の子供たちや、なりわいを探す母たちのもとへと広まっていく。これは、甘いポン菓子に人生をかけ、激動の時代を強く生き抜いた女性の物語──。
■「一生懸命働いておれば、子供たちもまっすぐ育つ」。ほぼ寝ずに全国を営業して
「『ドカン』と鳴ったと同時に、ときどき煙と一緒に木の上まで飛ばされる子がいるから、気をつけろよー!!」
リヤカーを引いてやってきたポン菓子屋のおじさんの口上に、集まった子供らの顔がこわばる。それでも、いざポン菓子ができあがると、甘くてサクサクの食感に、どの子供にもとびきりの笑顔がはじける。
昭和40年代まで、日本各地で見られた光景だ。地域によっては、その大音響の印象のまま“ばくだん”と呼ばれていることも。
利子さんが言う。
「ポン菓子を食べた子供たちは、『おいしい、おいしい』と大喜びで、それを見た私も本当にうれしくなったもんでした」
国産ポン菓子機1号機完成の翌年に吉村製作所を設立。一方家庭では、さらにその2年後より、利子さんは子宝を得て3男1女の母となる。
「私が一生懸命に働いておれば、子供たちもその背中を見てまっすぐに育つと信じとった。だから私は、とにかく自分の仕事を大切にしてきたんよ」
この言葉のとおり、三男の雄三さん(73)が覚えているのは、いつも工場にいた両親の姿だ。
「この母の記憶は、ほとんど働いている姿だけ。元教師だけあって、ふだんの挨拶などのしつけは厳しかったです。私が小学生のころは、3日に1台のペースで親父がポン菓子機を作るのを見てました。しかしその父も深酒のせいか、胃がんがもとで52歳の若さで亡くなりました」(雄三さん)
鉄鋼職人だった利子さんの夫・文夫さんの逝去は、1967年のこと。このころには、ポン菓子は定番のおやつとしてすっかり定着していた。急増する注文をこなす重圧は、一人、利子さんの小さな肩にのしかかっていく。夫に代わり工場を仕切り、最盛期には60人もいた職人を束ね、さらには自ら徹夜で鉄を削る作業をするようにもなる。機械に薬指を挟まれる大ケガをしたのも、このころだ。
先の大阪万博が開催された1970年ごろ、40代の利子さんの睡眠時間は1日3時間。需要に応えるべく、ポン菓子機と共に日本中を営業してまわっていた。さらに、国が米の消費拡大運動を展開したことや、いわゆる脱サラブームも手伝い、まさに“飛ぶように”売れた。’70年代半ばには、年間2千台が出荷されたという。
「工場で働きづめでも、母の口から『きつい、おなかすいた、眠い』を聞いたことがありません。子供心に、お母ちゃんはいつ寝てるんやろう、と不思議でした。営業では海外へも行って、たしかハイチがいちばん遠かったと。テレビで当時の世界最貧国と知って、居ても立ってもいられなくなったようです」(真貴子さん)
利子さん自身も、当時をこう振り返る。
「工場でケガもヤケドもしたけど、生きていくのに必死やったの。月に100カ所まわったことも。海外なんて、まわりは反対しましたが、ポン菓子のために死ぬなら本望という気持ちやったからね」
今も作業場に掲げられている、「ポン菓子機こそ我が命」の色紙も、この時期に自らしたためたものだ。しかし、社会がどんどん豊かになるにつれて、子供のおやつを取り巻く状況も大きく変わっていく。
’80年代になると、多種多様なスナック菓子が隆盛となり、ポン菓子の人気にも陰りが見え始める。そこに鉄工業そのものの不振も加わり、’98年には工場を閉鎖。以降利子さんは、主に販売や修理、イベントでの実演を中心に担うようになっていく。18歳で北九州にやってきた利子さんも、72歳になっていた。
「それでも私は朝5時半には起きて、事務所に顔を出してたよ。幸いポン菓子機の仕事も、子供たちが引き継いでくれたから」
’99年には、ポン菓子機の製造を三男の雄三さんが継いだ。続いて’02年には、上京した長男の文明さんが「ポン菓子機販売」を設立して、新企画の商品を展開していく。実は文明さんは、母親と同じ教職に就きながら心機一転、新天地での起業を果たしたのだ。
「両親の仕事を継承したいとの思いでした。時代に合わせてコンパクトなポン菓子機で勝負しようと考え、弟に頼んで、小型でスタイリッシュな型を開発したり。私も元教師ですから、ゲームにばかり夢中になっている現代の子供たちに、ポン菓子機を通じて、目の前で起きるドキドキの生身の体験をさせてやりたかった」(文明さん)
利子さんと長女の真貴子さんは、製造の一線からは身を引き、修理や使用法の指導を受け持つように。
「小学校や子供会からの依頼を受けて実演に行ったり。『ドカン!』という音を聞いて喜んでる子らを見ると、かつての飢えた教え子を思い出して、ようやく日本も平和になったんやな、と思いました」
こう利子さんが言えば、文明さんたちきょうだいも口をそろえて、かつて工場に届いた手紙について語った。
「戦後の復興のなか、ポン菓子機で商売をして家族を養った人も多かったんです。『ポン菓子機のおかげで、子供を大学の医学部にやることができました』という手紙をよく覚えてます」(文明さん)
1世紀の年月をポン菓子機と共に生き抜いてきた利子さんは、一見、平和で豊かに見える現代を生きる子供たちとお母さんへ、こんなメッセージをくれた。
「子供たちへ。自分だけじゃなく、みんなのことも考えてあげてね。そして、お母さん。平和というのは、家族がいつも一緒におること。あの戦争の時代は、それが失われてしもうたから。それがいちばん大事ということ、どうか忘れんでくださいね」