健康
926 ~950件/2460件
-

免疫力が上がる新習慣「マインドフロ(風呂)ネス」とは
2020/12/23 06:00心をリラックスさせる方法の一つである「マインドフルネス」。そのメソッドを毎日のバスタイムに応用すると、心と体にさまざまな効果が。さっそく今晩から始めてみようーー♪「長引くコロナ禍において、免疫力を高め、気分転換を図るためにも、バスタイムを有効活用しましょう。シャワーだけで済ませるのではなく、お湯をはった湯船にきちんと浸かることで、心と体にたくさんのメリットが得られます」温泉療法専門医で東京都市大学 -

湯船につかって深呼吸が免疫力アップに効く!専門家が指摘
2020/12/23 06:00「長引くコロナ禍において、免疫力を高め、気分転換を図るためにも、バスタイムを有効活用しましょう。シャワーだけで済ませるのではなく、お湯をはった湯船にきちんと浸かることで、心と体にたくさんのメリットが得られます」温泉療法専門医で東京都市大学人間科学部教授の早坂信哉先生はそう話す。早坂先生は入浴の健康効果を20年にわたり研究している入浴法のエキスパートだ。入浴による健康効果の代表が、温熱効果(温め効果 -

日本最高齢、89歳インストラクターに教わる「100歳まで歩ける簡単タキミカ体操」
2020/12/22 11:00本格的な冬の寒さと新型コロナの状況もあいまって、体を動かす機会が減ってませんか?やっぱり自分の足でちゃんと歩いて、ずっと元気に過ごしたい。なら、この人に注目。今日本中で話題騒然! SNSはじめ女性誌『美ST』のYouTubeなどでバズりまくりの、御年89歳の日本最高齢フィットネスインストラクターのタキミカさんこと瀧島未香さん。トレーニングを始めたのは、65歳のとき家族に「太ったんじゃない?」と言わ -

心身をリラックスさせ、自然治癒力高める「臭活」のススメ
2020/12/17 15:50認知症の改善や痛みの緩和、介護する側の心のケアなど、香りを活用した「アロマセラピー」の必要性と効果が今、介護の現場で注目を集めている。実際、香りにはどんな効果があるのだろう。予防医学にも詳しい、セラピストの有藤文香さんに話を聞いた。「アロマセラピーは、エッセンシャルオイルを使った、古くからある自然療法です。エッセンシャルオイルとは、精油やアロマオイルとも呼ばれますが、植物の香り成分を抽出したエッセ -

香りで効果アップ!「臭活」専門家教える「アロママッサージ入門」
2020/12/17 15:50ラベンダーやミントに代表される植物の香りには、心身の不調を改善する力がありました。「臭活(しゅうかつ)」とは、嗅覚をきたえ、香りでセルフケアすること。体、心、そして脳まで元気で長生きするために、今日からぜひーー!認知症の改善や痛みの緩和、介護する側の心のケアなど、香りを活用した「アロマセラピー」の必要性と効果が今、介護の現場で注目を集めている。実際、香りにはどんな効果があるのだろう。予防医学にも詳 -

大病院の初診7000円に!“かかりつけ医”が節約につながる
2020/12/16 06:00「現状、大学病院などの大病院を初めて受診する際、紹介状がないと、診察料とは別に5,000円以上の負担があります。その負担が引き上げられる可能性があるのです」こう話すのは、国の医療制度に詳しい社会保険労務士の石田周平さん。厚生労働省の諮問機関・社会保障審議会において、前述の費用を引き上げる方向で現在、議論がなされていると、11月19日付の読売新聞で報じられた。厚労省担当者は、本誌の取材に対し「『いつ -

病気の早期発見・予防で節約!脳梗防げば生涯450万円の差に
2020/12/16 06:00病気になってもポックリとは逝けずに、お金を払って生きながらえる。それが、医療が発達した令和の現実。大病を防いで、健康でいるのがなによりの節約につながるのだーー。「現状、大学病院などの大病院を初めて受診する際、紹介状がないと、診察料とは別に5,000円以上の負担があります。その負担が引き上げられる可能性があるのです」こう話すのは、国の医療制度に詳しい社会保険労務士の石田周平さん。厚生労働省の諮問機関 -

有名女医も実践する「1日2杯の紅茶」で14年間インフル知らず?
2020/12/15 11:0011月27日、奈良県立医大が市販の各種お茶に新型コロナウイルスを不活性化(無害化)する効果があると発表した。ウイルスが入った液体に市販のペットボトル入り緑茶2種類、茶葉から入れた紅茶、大和茶(奈良県で生産される日本茶)の計4種類をそれぞれ混合し作用を調べた。その結果、30分後に紅茶は99.99%、大和茶は99.9%までウイルスが減少。ペットボトルの緑茶1種類は99%まで減り、別の緑茶はあまり変化が -

年末に向け高血圧リスク増大!専門医が教える正しい血圧測定法
2020/12/14 06:00「今年はコロナ禍により、多くの人が家にこもりがちになりました。食事量は変わらない、むしろストレス解消のために過食気味になっているのに、運動量は減り、体重が増加した人も多いでしょう。摂取カロリーが増え、家飲みなどで酒量が増えると、高血圧になるリスクが高まるのです」そう警鐘を鳴らすのは、“Dr.血圧”として名高い、高血圧を中心とした循環器病の専門医・渡辺尚彦先生。渡辺先生自身、87年8月より連続して携 -

コロナ禍でリスク高まる 高血圧防ぐ生活習慣
2020/12/14 06:00高血圧は男性に多いイメージがあるが、実は40歳を過ぎると女性も徐々に血圧が高くなる傾向がある。更年期になると女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの減少にともない、血圧をコントロールしている自律神経の働きが乱れて、血圧が上がってしまうのだ。「自分は低血圧だ」と思いこんでいる女性は多いが、久々に測定してみたら高血圧になっていたなんてこともあるのだ。「今年はコロナ禍により、多くの人が家にこもりがちにな -

リハビリ現場で実証…「フラワーアレンジ」の脳トレ効果
2020/12/13 11:00花を愛でることによって心が癒されたり、リラックスできることを実感する人は多いだろうが、花を使ったフラワーアレンジメントが脳の認知機能にも関係していることは意外と知られていない。独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の上級研究員・望月寛子先生は、フラワーアレンジメントが脳の認知機能の改善、向上に役立つという研究結果を発表している。望月先生がフラワーアレンジメントに着目するようになった -

コロナ禍の今こそ…「花の画像」を眺めて血圧を下げる
2020/12/13 11:00「安静時に花を見ると副交感神経が優位になることから、『花には癒しの効果がある』と言われていました。今年6月に発表した研究では、さらに心理的ストレスによって上昇した血圧やホルモンを下げる効果が実証されました」農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)上級研究員の望月寛子先生はこう話す。これまでに、自然に囲まれた環境での血圧変化の研究はあったが、国内外で花による血圧降下やストレスホルモンの減少を実証し -

「魔の時間帯」避けると痩せる?3000人を減量させた医師の鉄則
2020/12/11 11:00在宅勤務、ステイホームが叫ばれた2020年。コロナ太りに悩まされる人も多い。その原因は運動不足、ストレス食い、生活リズムの乱れなどさまざまだが、浅原哲子医師は「夜型生活が危険だ」と警鐘を鳴らす。浅原先生は、20年近く京都医療センターの肥満・メタボリック外来で、3,000人以上のダイエットを成功に導いた専門医だ。肥満の実態をつぶさに見てきた浅原先生に、太る原因とその解消法を聞いてみた。「コロナ禍の在 -

3000人の肥満救った医師が伝授!楽ヤセへの「けじめ習慣」
2020/12/11 11:00コロナ禍でリモートワークやオンライン会議が推奨され、家で過ごす機会が増えた。すっかり出不精になってしまった人も多いのでは?「出不精は“デブ症”の元。肥満になると糖尿病、高血圧などが発症しやすく、動脈硬化が進行して、心筋梗塞や脳卒中など命にかかわるリスクも高まります。私は、『健康的に痩せる』ことを推奨しています」と話すのは、日本では数少ない肥満・メタボリック外来で、これまで3,000人以上のダイエッ -

朝スムージーも…いいと思ってやったのに“認知症”招くNG食習慣
2020/11/28 11:00日ごろの食事に関する誤った習慣が、認知症リスクを高めることになると医師は警鐘を鳴らす。そのなかには、体のためを思って多くの人がやりがちなものも。思い当たる項目があるという人はくれぐれもご注意をーー!2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという推計(’17年・厚生労働省)もあるなど、社会問題化している認知症。発症したくないと脳トレに励む人もいるだろう。だが“栄養番長”として知られる医師の -

“栄養番長”姫野友美医師「認知症を招く糖化による“サビ”にご用心」
2020/11/28 11:002025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという推計(’17年・厚生労働省)もあるなど、社会問題化している認知症。発症したくないと脳トレに励む人もいるだろう。だが“栄養番長”として知られる医師の姫野友美先生は、「脳の健康は、脳トレだけでは守れない」と話す。「大切なのは、脳に必要な栄養をしっかり取って、不必要なものは体内に入れないこと。『腸脳相関』といって、腸と脳は密接に影響し合っていること -

コロナ禍に知りたい 感染症対策は室温22度、湿度50%で
2020/11/27 06:00「日本人は、寒さを我慢したほうが体が鍛えられるとか、健康になると考える傾向があり、実際9割以上の人が寒い家に住んでいます。ところが、寒い住環境は健康寿命を縮めることがわかってきたのです」住環境と健康の関係に詳しいジャーナリストの笹井恵里子さんはこう話す。「2002年から高知県梼原町で、住居と健康の関係についての疫学調査が実施され、寒い住環境は、睡眠の質、筋肉量、脳の働き、血圧、コレステロール値とい -
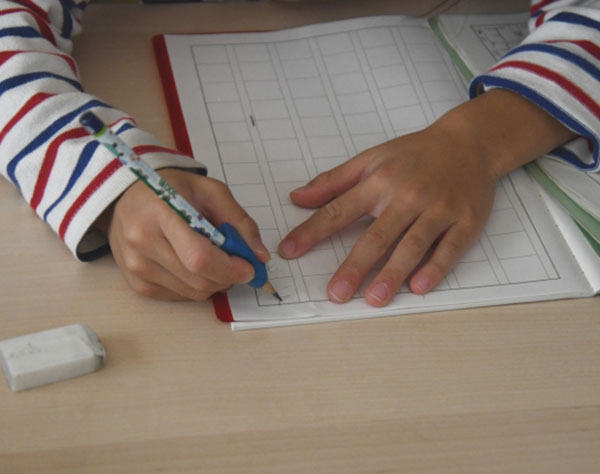
子供の学習に最適な室温は?健康寿命を延ばす冬の室温クイズ
2020/11/27 06:00日本人は寒さを我慢したほうが体が鍛えられると考える傾向にあるが、寒い住環境は、さまざまな病気に影響を与えているという。感染症に対する影響から、脳神経、血圧に対する影響、睡眠への影響、コスパのいい暖房方法などを知って、適度な室温で健康に暮らして、長生きしようーー!「日本人は、寒さを我慢したほうが体が鍛えられるとか、健康になると考える傾向があり、実際9割以上の人が寒い家に住んでいます。ところが、寒い住 -

ぽっこりおなかの原因“大腰筋”衰え度チェックリスト
2020/11/26 11:00コロナ太りに悩む読者世代たちの間で、へそから下の“ぽっこり下腹”が気になるという人が続出している。「脂肪太りだけが原因ではありません。内臓が正常の位置よりも下がり、腸が圧迫されて前に突き出て、おなかがせり出してしまっている“内臓下垂”の可能性があります。人の体は骨格という基礎の上に筋肉の土台があり、その表面を脂肪が覆っています。ホルモンの分泌量や活動量が減ってくる40代以降になると、下腹部やお尻、 -

岡田隆先生伝授「内臓下垂を予防する大腰筋エクササイズ」
2020/11/26 11:00おへそから下がぽっこりと出てしまう“内臓下垂”。「背骨を引っぱる」「骨盤を支える」「太腿を上げる」働きをする大腰筋を鍛えれば、悩みは解消ーー!コロナ太りに悩む読者世代たちの間で、へそから下の“ぽっこり下腹”が気になるという人が続出している。「脂肪太りだけが原因ではありません。内臓が正常の位置よりも下がり、腸が圧迫されて前に突き出て、おなかがせり出してしまっている。“内臓下垂”の可能性があります。人 -

コロナ禍の不安でスイッチが…「夫の精神疾患」が増加中
2020/11/26 06:00「新型コロナウイルスに起因する生活不安やストレスなどにより、DV(ドメスティックバイオレンス)の増加や深刻化が懸念されております」10月8日の参議院内閣委員会において、林伴子内閣府男女共同参画局長はこう答弁した。この問題は、新型コロナウイルスの“第3波”によって、より深刻さを増す可能性が高い。全国の「配偶者暴力相談支援センター」に寄せられた5と6月のDV相談件数は、前年比でそれぞれ1.6倍増で計約 -

コロナ禍、優しかった夫が豹変し暴言を…専門家が語る実例
2020/11/26 06:00コロナ以降、社会を取り巻く生活環境は激変した。不安やストレスを抱えた夫や妻が“ある日突然”、統合失調症や双極性障害、そしてうつ病といった精神疾患を発症するケースが増えているという。「コロナ禍という環境が原因だと断定できる統計資料はまだありませんが、“夫が急変してしまった”という配偶者からの相談件数が増えているのは確かです」こう語るのは、杏林大学保健学部作業療法学科の助教で、「精神に障害がある人の配 -

「ヨーグルトなら何でも大腸にいいはNG」と医学博士
2020/11/25 11:00「何日も排便がない状態や、便通があったのにまだ残便感がある、などの異変は大腸がダメージを受けている証拠。これは“大腸劣化”のわかりやすいサインです」帝京平成大学の松井輝明教授はそう警鐘を鳴らす。便秘などによって腸内の悪玉菌が増加した状態を放置していると、腸内環境、特に大腸の劣化が進むという。大腸劣化は肌トラブルや肥満、さらには大腸がんや認知症などさまざまな病気のリスク要因になるというから注意が必要 -

更年期をむかえるころの女性は“大腸の劣化”に要注意
2020/11/25 11:00最近よく耳にする、腸内環境の大切さ。それは主に、大腸のコンディションを指す。あなたの大腸が“劣化”してしまっている恐れがないか、自分の生活と照らし合わせてみよう。早めの改善が鉄則です−−!「何日も排便がない状態や、便通があったのにまだ残便感がある、などの異変は大腸がダメージを受けている証拠。これは“大腸劣化”のわかりやすいサインです」帝京平成大学の松井輝明教授はそう警鐘を鳴らす。便秘などによって腸 -

鍼灸師が提言、ひざ痛の人のための「足の甲のばし」
2020/11/23 11:00ひざ痛をはじめとして、腰痛や外反母趾などの不調の原因は“浮き指”にあると世界的メディカルトレーナーは語る。足の指を鍛えて、10本の足で地面をしっかりつかめるようになると、不調も改善−−!「これまでのべ12万人以上の足をケアしてきましたが、ひざや腰に痛みを抱える人のほとんどが、足の指がしっかり地面についていない“浮き指”状態なんです。これを改善する切り札が『足の甲のばし』なんですよ」こう話すのは『1

