健康
1151 ~1175件/2460件
-

パン類、洋菓子持つ“超悪玉コレステロール”リスクを医師が警鐘
2020/03/08 11:00「コレステロールは、私たちの体の細胞壁やホルモンの材料となるなど、生きるうえで必要不可欠なものです。ところが、誤った食生活によって悪影響をうけると、血管壁に蓄積して動脈硬化の原因となり、逆に体に悪影響を与えてしまうこともあるのです」こう話すのは内科医で動脈硬化に詳しい池谷敏郎先生。偏った食生活はコレステロールの“暴走”を起こすという。「コレステロールは体内でLDLコレステロールとして血管壁に運ばれ -

医師が警告する「女性襲う病気」、予防のカギは「女性ホルモン」
2020/03/05 15:50原因もわからずに、ある日突然襲い掛かる病気には、中高年の女性に患者が多く見られるものがある。そんな疾患を、少しでも遠ざけるために日ごろからできることとはーー。「体のどこかがいつも激しく痛む」「肘のあたりが急に腫れた」など、ある日突然襲い掛かる体の不調に悩む40〜50代の女性は多い。「特にけがをしたというわけではないのに、体のどこかに不調が出てくることには、女性ホルモン『エストロゲン』の低下が関係し -

変形関節症、肺MAC症…女性罹りやすい「原因不明の病気」たち
2020/03/05 15:50「体のどこかがいつも激しく痛む」「肘のあたりが急に腫れた」など、ある日突然襲い掛かる体の不調に悩む40〜50代の女性は多い。「特にけがをしたというわけではないのに、体のどこかに不調が出てくることには、女性ホルモン『エストロゲン』の低下が関係していると考えられます。女性は45歳を過ぎたころから女性ホルモンの分泌が減少し始め閉経に向かい、のぼせ・ほてりなどのホットフラッシュ、めまいや動悸といった症状が -

中之条町の人に聞くー病気防ぐ8千歩・20分早歩きはキツい?
2020/03/05 11:00群馬県の北西部に位置する人口約1万5,000人の中之条町。この小さな町で行われている研究から生まれた歩き方が生活習慣病を予防し、健康寿命まで延ばすとして世界から注目を集め“中之条の奇跡”とまで呼ばれている。研究を主導している東京都健康長寿医療センター研究所・社会参加と地域保健研究チーム専門副部長の青柳幸利先生が解説する。「’00年から20年にわたって5,000人を超す人を対象に調査を行ってきました -

「病気リスク下げる歩き方」実践の町、70〜74歳医療費は半分に
2020/03/05 11:00群馬県の北西部に位置する人口約1万5,000人の中之条町。この小さな町で行われている研究から生まれた歩き方が生活習慣病を予防し、健康寿命まで延ばすとして世界から注目を集め“中之条の奇跡”とまで呼ばれている。研究を主導している東京都健康長寿医療センター研究所・社会参加と地域保健研究チーム専門副部長の青柳幸利先生が解説する。「’00年から20年にわたって5,000人を超す人を対象に調査を行ってきました -

がんリスク抑止に期待…20年の研究で発見!病気を防ぐ歩き方
2020/03/05 11:00「主人の母を介護していた10年前から血圧とコレステロール値が高くて薬を飲んでいました。でも5年前に、町の保健センターの人に勧められて歩くようになってからは、薬に頼らなくても血圧が安定し、コレステロール値も改善。子どもたちからも『年のわりに若いよ』と言われるんです」こう語るのは、中之条町で暮らす主婦の遠田敏子さん(70)。群馬県の北西部に位置する人口約1万5,000人の中之条町。この小さな町で行われ -

めまい、頭痛、更年期障害…“首こり”が引き起こす不調
2020/03/04 15:50いまや日本人の国民病ともいえる「肩こり」。とりわけ女性の悩みは深く、厚生労働省の調査によれば、「腰痛」や「手足の関節が痛む」などを抑え、女性の体の悩みの第1位(平成28年「国民生活基礎調査の概況」より)となっている。ちょうどいまの時期は、冬の寒さでこわばり「肩こりが悪化した」と感じる人も多いだろう。また「肩こりのせいで頭痛やめまいが……」という話を聞いたことがある人も少なくないのでは?でも、ちょっ -

15度傾くと筋肉への負担は倍増…“首こり病”の恐ろしさ
2020/03/04 15:50ちょうどいまの時期は、冬の寒さでこわばり「肩こりが悪化した」と感じる人も多いだろう。また「肩こりのせいで頭痛やめまいが……」という話を聞いたことがある人も少なくないのでは?でも、ちょっと待って! そのつらい“肩こり”は、じつは“首こり”の可能性が高いのです!「悪化することで頭痛やめまいを引き起こすというのは、肩こりではありません。それは“首”がこっているのです」そう語るのは、40年以上首の研究と治 -

医師が教える“首こり”対策法「ドライヤーは入浴後すぐ」
2020/03/04 15:50ちょうどいまの時期は、冬の寒さでこわばり「肩こりが悪化した」と感じる人も多いだろう。また「肩こりのせいで頭痛やめまいが……」という話を聞いたことがある人も少なくないのでは?でも、ちょっと待って! そのつらい“肩こり”は、じつは“首こり”の可能性が高いのです!「悪化することで頭痛やめまいを引き起こすというのは、肩こりではありません。それは“首”がこっているのです」そう語るのは、40年以上首の研究と治 -

頭痛をともなう肩こり、「それは“首こり”です」と専門医
2020/03/04 11:00いまや日本人の国民病ともいえる「肩こり」。とりわけ女性の悩みは深く、厚生労働省の調査によれば、「腰痛」や「手足の関節が痛む」などを抑え、女性の体の悩みの第1位(平成28年「国民生活基礎調査の概況」より)となっている。ちょうどいまの時期は、冬の寒さでこわばり「肩こりが悪化した」と感じる人も多いだろう。また「肩こりのせいで頭痛やめまいが……」という話を聞いたことがある人も少なくないのでは?でも、ちょっ -

歯科医勧める「歯ぐきマッサージ」リンパの流れ整える効果
2020/03/04 06:00足裏や手のひらと同様、口の中にもツボがあることをご存じだろうか。「口腔ケアは健康対策の最前線」という歯科医師・野本恵子先生によると、じつは、歯ぐきには40以上ものツボがあり、マッサージで刺激することによって、さまざまな効果が得られるという。「歯ぐきのツボは全身とつながっているので、刺激してあげることで不調や疲れの軽減、リラックス効果が期待できます。リンパの流れがよくなるので、老廃物も排出できますし -

生活習慣病予防にも、歯科医推奨の「歯ぐきマッサージ」方法
2020/03/04 06:00口腔ケアは健康対策の最前線! 歯ぐきをマッサージすることで口の中の健康維持はもちろん、全身の不調の改善、生活習慣病や認知症の予防までできるというーー。足裏や手のひらと同様、口の中にもツボがあることをご存じだろうか。じつは、歯ぐきには40以上ものツボがあり、マッサージで刺激することによって、さまざまな効果が得られるそう。「歯ぐきのツボは全身とつながっているので、刺激してあげることで不調や疲れの軽減、 -

現役女医が使っている市販薬、胃もたれには「ガスター10」
2020/02/27 15:50新型コロナウイルスの流行が止まらない。国内での感染者の数も増えるばかりで、外出はおろか、少し体調不良を感じても、病院にかかることがおっくうになるのが正直なところだ。「病院に行かなくても症状を軽減させるためには、薬局や薬店などで処方箋なしで購入できる市販薬(OTC医薬品)の使用が必須になってきます。市販薬の効果をきちんと理解し、症状に合わせて服用することで、自分自身の健康を管理することが求められてい -

現役女医が風邪の初期に飲む「葛根湯」は肩こりにも効果
2020/02/27 15:50新型コロナウイルスの流行が止まらない。国内での感染者の数も増えるばかりで、外出はおろか、少し体調不良を感じても、病院にかかることがおっくうになるのが正直なところだ。「病院に行かなくても症状を軽減させるためには、薬局や薬店などで処方箋なしで購入できる市販薬(OTC医薬品)の使用が必須になってきます。市販薬の効果をきちんと理解し、症状に合わせて服用することで、自分自身の健康を管理することが求められてい -

「花粉に負けない」基礎体力を作る「ストレッチ」と「足湯」
2020/02/27 06:00新型コロナウイルスの感染拡大がいまなお続くなか、今年も花粉症の季節がやってきた。東京都では、青梅市と八王子市で2月3日からスギ花粉の飛散開始を確認したという。飛散開始は、過去10年の平均(2月17日)より14日、昨年より8日も早い。「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです。今年のスギ花粉の飛散のピークは、東京では2月下旬から3月下旬まで。飛散の収束時期は例年とあまり変わらない見込み -

花粉を家に持ち込まないための「帽子で外出+徹底洗顔」
2020/02/26 15:50「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです。今年のスギ花粉の飛散のピークは、東京では2月下旬から3月下旬まで。飛散の収束時期は例年とあまり変わらない見込みで、これはつまりピークが例年よりも長い期間となるということです。さらにスギ花粉のピークが終わるころになると、今度はヒノキの花粉が飛び始めます。ヒノキの飛散のピークは東京で4月上旬から下旬まで続きます」そう話すのは、日本気象協会の気象 -

花粉症の時期に「夕食時の飲酒」控えるべき理由は“脱水状態”
2020/02/26 15:50新型コロナウイルスの感染拡大がいまなお続くなか、今年も花粉症の季節がやってきた。東京都では、青梅市と八王子市で2月3日からスギ花粉の飛散開始を確認したという。飛散開始は、過去10年の平均(2月17日)より14日、昨年より8日も早い。「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです。今年のスギ花粉の飛散のピークは、東京では2月下旬から3月下旬まで。飛散の収束時期は例年とあまり変わらない見込み -

花粉症患者に医師「『市販薬あるから病院いかない』は危険」
2020/02/26 11:00「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです」そう話すのは、日本気象協会の気象予報士、堀口貴司さん。新型コロナウイルスの感染拡大がいまなお続くなか、今年も花粉症の季節がやってきた。東京都では、青梅市と八王子市で2月3日からスギ花粉の飛散開始を確認したという。飛散開始は、過去10年の平均(2月17日)より14日、昨年より8日も早い。「今年のスギ花粉の飛散のピークは、東京では2月下旬から3 -

「花粉症」防ぐ為の“朝習慣”布団干すなら「昼まで」にが吉
2020/02/26 11:00「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです。今年のスギ花粉の飛散のピークは、東京では2月下旬から3月下旬まで。飛散の収束時期は例年とあまり変わらない見込みで、これはつまりピークが例年よりも長い期間となるということです。さらにスギ花粉のピークが終わるころになると、今度はヒノキの花粉が飛び始めます。ヒノキの飛散のピークは東京で4月上旬から下旬まで続きます」そう話すのは、日本気象協会の気象 -

増え続ける「花粉症」患者、「症状悪化する可能性も」と専門医
2020/02/26 06:00新型コロナウイルスの感染拡大がいまなお続くなか、今年も花粉症の季節がやってきた。東京都では、青梅市と八王子市で2月3日からスギ花粉の飛散開始を確認したという。飛散開始は、過去10年の平均(2月17日)より14日、昨年より8日も早い。日本気象協会の気象予報士、堀口貴司さんに、今シーズンの飛散状況を解説してもらった。「これほど早く花粉が飛散したのは暖冬の影響によるものです。今年のスギ花粉の飛散のピーク -

「いま8人に1人が慢性腎臓病」専門医が語る“病のサイン”
2020/02/20 15:50「いまや成人の8人に1人が『慢性腎臓病』にかかっている。これは、“国民病”といわれる糖尿病の患者より多いのです。しかも慢性腎臓病は、かなり症状が進行しないと自覚症状が現れません」そう警鐘を鳴らすのは、東北大学大学院教授を務める腎臓専門医の上月正博先生だ。血液をろ過して、老廃物を体外に排出する機能を持つ腎臓。血液や骨の組成、そして血圧の維持にも関係しており、生命維持に欠かせない臓器だ。「腎臓の機能が -

専門医指導する「慢性腎臓病」予防「20分×週5回歩こう」
2020/02/20 15:50「腎臓の機能が低下してしまうと、通院で回復させるのは難しい」。腎臓内科の医師はそう語る。健康な腎臓を保つためには、多少“キツい”運動も心がけるべしーー。「いまや成人の8人に1人が『慢性腎臓病』にかかっている。これは、“国民病”といわれる糖尿病の患者より多いのです。しかも慢性腎臓病は、かなり症状が進行しないと自覚症状が現れません」そう警鐘を鳴らすのは、東北大学大学院教授を務める腎臓専門医の上月正博先 -

京丹後市ご長寿の暮らしに密着、手作り料理のメニューに秘密が
2020/02/19 15:50100歳以上の割合が高く、80代、90代が自立して生き生きと暮らす町。その秘密は生活環境にあり。昔ながらの食生活が守られ、腸内環境が整っているのも大きな理由とかーー。日本は世界でトップクラスのご長寿大国だが、なかでも今、100歳以上の“百寿者”がたくさんいる京都府北部の町、京丹後市に注目が集まっている。京都駅から特急で2時間半、丹後半島にある海沿いの町で、漁業と江戸時代から続く丹後ちりめんが有名。 -
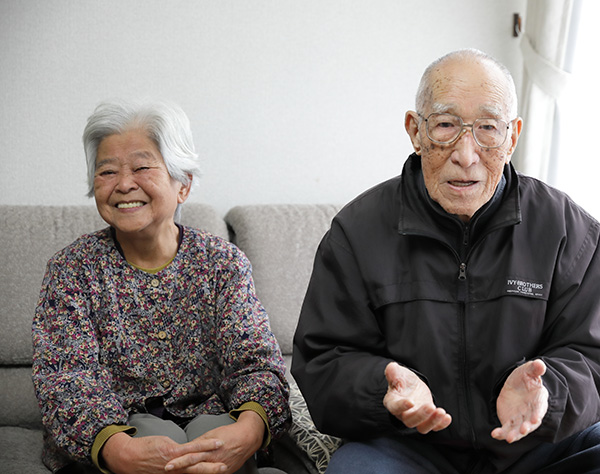
“長寿の町”京丹後市 お年寄りも「自分たちのこと自分でやる」
2020/02/19 15:50100歳以上の割合が高く、80代、90代が自立して生き生きと暮らす町。その秘密は生活環境にありーー。日本は世界でトップクラスのご長寿大国だが、なかでも今、100歳以上の“百寿者”がたくさんいる京都府北部の町、京丹後市に注目が集まっている。京都駅から特急で2時間半、丹後半島にある海沿いの町で、漁業と江戸時代から続く丹後ちりめんが有名。人口あたりの“百寿者”の比率が全国平均2.8倍(’16年時点)で、 -

京丹後市の94歳現役営業マン、就寝時間は「日付変わってから」
2020/02/19 11:00100歳以上の割合が高く、80代、90代が自立して生き生きと暮らす町。その秘密は生活環境にありーー。日本は世界でトップクラスのご長寿大国だが、なかでも今、100歳以上の“百寿者”がたくさんいる京都府北部の町、京丹後市に注目が集まっている。京都駅から特急で2時間半、丹後半島にある海沿いの町で、漁業と江戸時代から続く丹後ちりめんが有名。人口あたりの“百寿者”の比率が全国平均2.8倍(’16年時点)で、

