リスクの最新ニュース
1 ~25件/46件
-

岸田首相 高齢者の定義「70歳引き上げ」で年金1300万円減!労災死増加の懸念も
2024/06/06 06:00現在、65歳以上となっている高齢者の定義。これを5歳引き上げようという提言が話題になっている。これが招くのは年金の大幅な減額と、高齢者の労災の続出だ。頼みの綱の賃上げも、不都合な真実が明らかになって――。「高齢者の健康寿命も延びるなか、“高齢者”の定義を5歳引き上げるべき!」岸田文雄首相(66)も出席した経済財政諮問会議で5月23日、経団連のトップたちから、そんなトンデモ提言が飛び出した。現在、日 -

2050年に高齢独居女性が直面する「悲惨予想図」年金減額で月4万円以上の大赤字に
2024/05/27 11:00「4月24日に発表された有識者グループ・人口戦略会議のレポートで、少子化によって2050年までに、全国の市区町村の4割にあたる744もの自治体に“消滅可能性がある”と報告されました。将来的に、路線バスなどが廃線になり、買い物難民になったりと、満足な行政サービスが受けられなくなる可能性が指摘されています。また、医学が発達して長寿化すれば、医療や介護の期間も長くなります。その一方で、赤字体質の自治体で -

「危険すぎる」居酒屋で提供された“生の豚レバー”にSNS震撼 保健所が明かす生食のリスク
2024/05/24 06:005月中旬、X上である”レバテキ”の写真が大きな注目を集めた。それは都内に店を構える居酒屋が”名物”として提供していたもの。一見すると美味しそうだが、メニューを説明する看板には豚レバーを“サッと炙って”提供しているとの記述があり、写真では確かに肉の内部に赤みのあるレアの状態だった。平成27年6月12日から食品衛生法に基づき、豚の肉や内臓を生食用として販売・提供することは禁止されている。この投稿は30 -

「家賃11万円以上」の賃貸に住む50代夫婦が知らない意外な“老後破綻リスク”
2024/05/22 11:00高齢者は賃貸を借りづらい。よく言われることだが、それを裏付ける調査結果が発表された。賃貸に住む人たちは、今後どうすればいいのか。専門家と考えた。賃貸派の人が驚愕するデータが発表された。全国の賃貸物件のオーナー500名に聞いたアンケート調査で、「高齢者の入居を受け入れていない」と答えた賃貸オーナーが41.8%もいたというのだ。なぜ高齢者の入居を避けるのだろう。高齢者の住まいに詳しいファイナンシャルプ -

厚労省の飲酒ガイドライン“ロング缶1本”に悲鳴「休肝日あればもっと飲んでいい?」疑問に回答
2024/02/24 06:00厚生労働省は2月19日、アルコールによる健康へのリスクを知って不適切な飲酒を減らすための参考となるよう、飲酒に関する初のガイドラインを公表した。ガイドラインには疾病別の発症リスクと飲酒量についての記載があり、大腸がんは男女ともに週150g(1日20g)、脳梗塞については男性週300g(1日40g)・女性週75g(1日11g)以上の飲酒をすると、それぞれ発症等のリスクが高まると考えられていると例示さ -

女性のは副作用のリスク2倍! 目的外使用の「痩せ薬」で腸閉塞に…
2024/02/02 11:00「すでに痩せているのに美容やダイエットの目的で糖尿病治療薬を利用することは非常に危険です」とは、これまで延べ20万人以上の糖尿病患者を診てきたAGE牧田クリニックの牧田善二院長。美容のために痩せたいと、オンライン診療で処方された糖尿病治療薬購入によるトラブルが相次いでいる。問題になっているのが「GLP-1受容体作動薬」だ。「2型糖尿病の治療薬としては画期的な薬です。ヒトが食事をすると小腸からGLP -

大人もマイコプラズマ肺炎感染で重症化リスク! 医師が警鐘「インフル同時感染の可能性も」
2023/12/27 06:00「この肺炎は、子供から高齢者まで、幅広い世代に感染します。なかでも5歳から15歳以下の子供に感染しやすく、全体の約5割を占めるともいわれています。ただし、子供からの飛沫や接触によって、家庭内感染で大人にうつるケースも多く、65歳以上の高齢者が感染した場合、重症化しやすいので注意が必要です」こう警鐘を鳴らすのは、日本感染症学会専門医で、東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺嶋毅教授。全国でインフルエ -

お米2kgにおせちまで…“投資歴20年主婦”まる子さんが語る奥深き株主優待の世界【後編】
2023/12/26 11:00「株の投資にはリスクがつきものなので、余剰資金の範囲内で投資するのは基本ですが、数千円のお小遣いの範囲から10万円程度で優待の権利が得られる株もあります。どの株に投資したらいいのか、わからないという人は、10万円未満で、QUOカードや商品券などの優待品がもらえる株に投資することを始めてみるのも良いでしょう。いつも利用する飲食店の飲食券やスーパーや、化粧品や日用品など身の回りのものが優待品になってい -
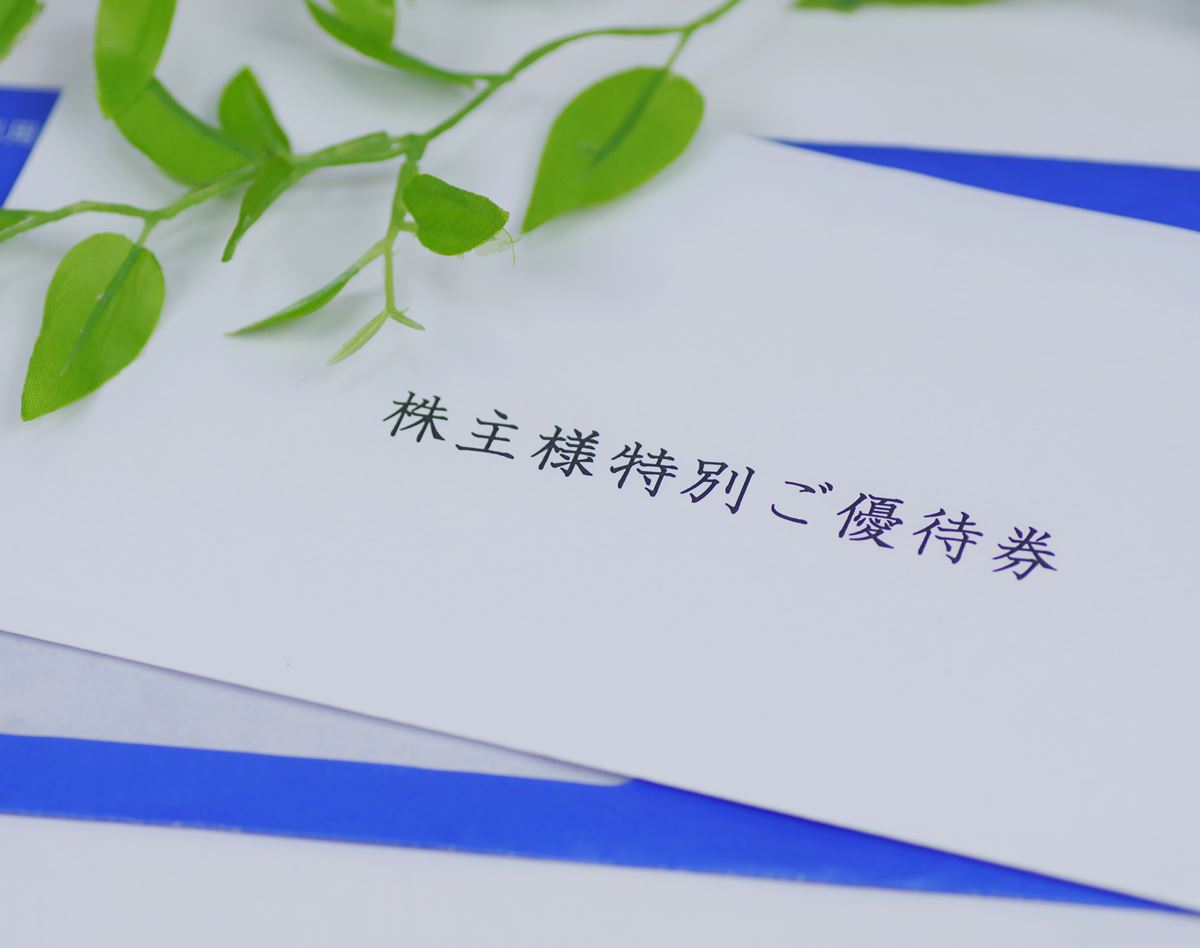
「株を買い増していたら200以上に」優待主婦まる子さんが語る“入門者が知るべき2つのポイント”【前編】
2023/12/26 11:00株の投資を始めたいと思っても、「投資は怖い」と思うあまり一歩が踏み出せないという人は意外と多い。「株式投資の経験がゼロでも、企業から商品や商品券などがもらえる株主優待を活用すれば、お小遣いレベルの金額でも十分に楽しめますよ」と語るのは、人気ブロガー・優待主婦まる子さん。約20年前から株式投資を始めて、現在200以上の株を持つ。毎日1〜2個届く「優待品」を満喫する様子をブログに綴っている。「当時勤め -

激しい寒暖差で発症——「目の動脈硬化」で朝起きたら失明のリスクも!
2023/11/29 11:00視界がぼやける、かすむ……よくあると放置しがちな目のトラブル。ある日突然、目覚めたら目が見えないなんてことになる前にーー。都心では、100年ぶりに11月の最高気温を更新し、各地で異例の暑さが続いていたが、師走の足音が近づいたら、急激な冷え込みが訪れた。「今年のように寒暖差が激しい冬は、例年以上に注意すべき目の病いがあります。処置が遅れると“失明”につながることもあるので、十分な注意が必要です」そう -

睡眠が2時間不足でうつや不安障害リスク…「脳冷やし」で快眠、健康なメンタルへ
2023/11/01 15:50実際の睡眠時間が、理想の睡眠時間から2時間不足する人の約3割は、うつ病や不安障害の疑いがある……。政府は10月13日に’23年版「過労死等防止対策白書」を公表。そのなかで、睡眠時間と精神疾患の関係についての調査結果に言及している。まず、理想の睡眠時間は半数近くが「7~8時間」と答え、「6~7時間」と合わせると8割近くに。しかし、実際の睡眠時間は「5~6時間」がもっとも多い。次に、理想の睡眠時間が確 -

“彼氏と2ショット撮らない”ホラン千秋のリスク管理に出川哲朗はドン引き…ネットは「悲しい」「賢い」と賛否真っ二つ
2023/10/11 18:06タレントの出川哲朗(59)が10日に放送された『秋の爆笑さんま御殿!!3時間SP』(日本テレビ系)に出演し、「この人無理だ」と思った女性タレントとしてホラン千秋(35)を名指し。その理由となったホランの“過去の行動”に対して、ネット上では賛否が真っ二つに割れている。同番組内の「この人とは絶対無理!と思う異性のタイプ」という話題の際に、「ホラン千秋という人なんですけど」と同じくゲスト出演しているホラ -
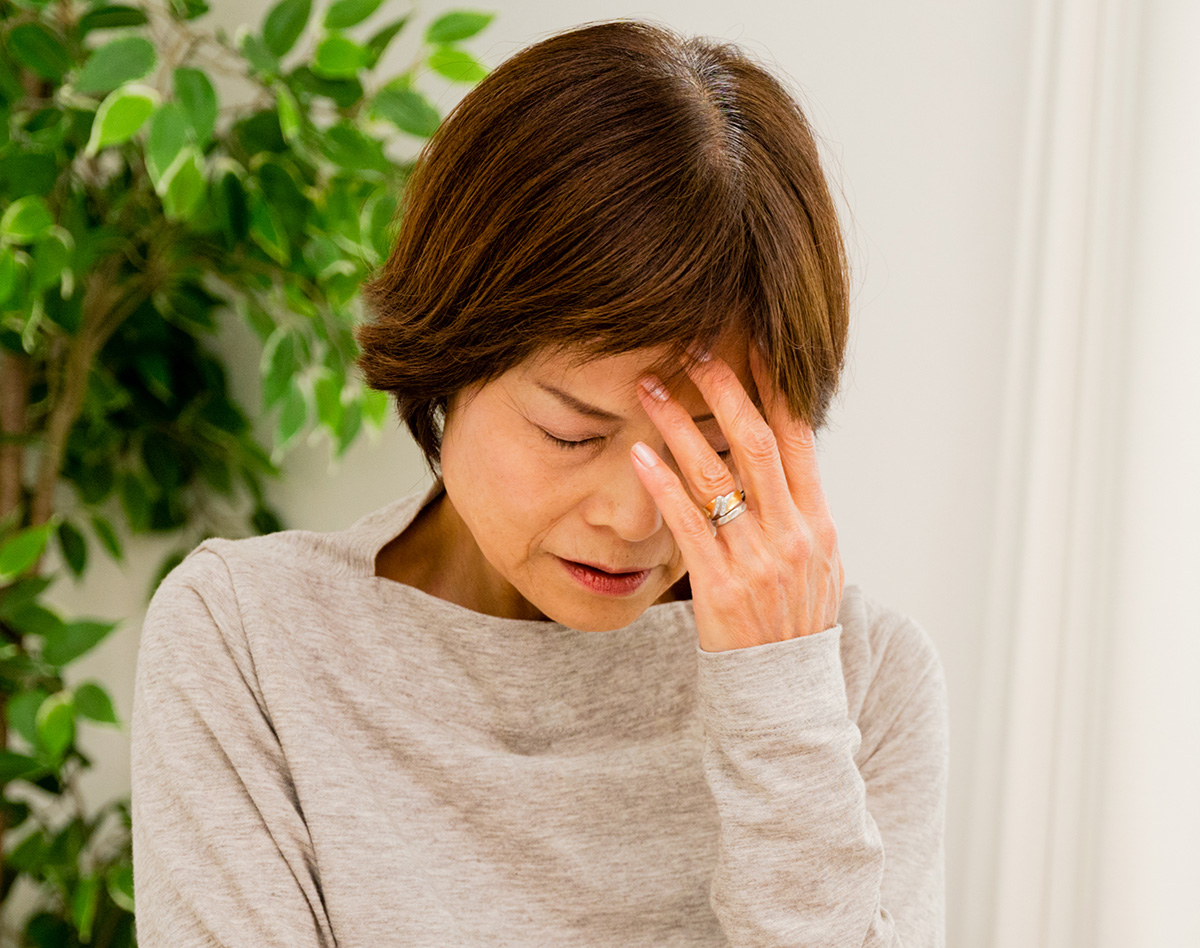
60代の40%が悩む夜間頻尿 夜2回以上のトイレは死亡リスクは2倍に!
2023/08/25 06:00「夜中にトイレで1~2回起きるのは、年なんだから仕方ない」そう思ってはいないだろうか。「就寝後にトイレで2回以上起きる高齢者は、1回以下の高齢者より、死亡率が1.98倍上昇するといわれます。『夜間頻尿』は見過ごすことのできない病気です」そう警鐘を鳴らすのはマイシティクリニック院長で『老化を「栄養」で食い止める 70歳からの栄養学』の著者、平澤精一先生だ。夜間頻尿とは、就寝後1回以上トイレに起きなけ -

カロリー0の人工甘味料が危ない!糖尿病や重大疾患を招く可能性をWHO指摘
2023/06/29 15:50“カロリーゼロ”や“低カロリー”のダイエット食品に使われる人工甘味料に、長期的なダイエット効果は期待できないーー。5月15日にWHO(世界保健機関)が発表したガイドラインが波紋を呼んでいる。WHOは283件の研究報告を分析。人工甘味料を含む非糖質系甘味料は、3カ月など短期間の使用では体重や体格指数(BMI)を下げる効果があるが、6〜18カ月の長期間だと減量効果が見られないという。非糖質系甘味料とは -

「酒が弱い人の飲酒」で胃がんリスク増……体質セルフチェック法
2023/03/30 06:00「お酒に弱い人、つまりアルコールを分解しにくい体質の人がお酒を飲むと、胃がんを発症するリスクが高まることが、新たな研究結果からわかりました」こう話すのは、国立がん研究センター研究所がんゲノミクス研究分野長の柴田龍弘先生だ。胃がんは全体の約7割が「腸型」、約3割が「びまん型」と、大きく2種に分類される。腸型の胃がんはピロリ菌感染が原因とされているが、びまん型の胃がんの発症原因は「まだ解明されていない -

衝撃の新研究…おしりの洗浄1日2回以上で“おもらしリスク”急上昇!
2022/11/28 11:00《温水洗浄便座を1日2回以上使用する人は、便失禁が重症化する》10月14日、第77回日本大腸肛門病学会学術集会で発表された研究報告に注目が集まっている。排便後のお尻洗浄は、今や私たちが日常的に行うルーティン。だが、過度な洗浄が“うんち漏れ”のリスクを高めるというのだ。「今回のデータは、便失禁のある37〜92歳までの患者さんを対象に、4週間、温水洗浄便座の使用をやめていただき、症状の変化を評価しまし -

運転期間「上限撤廃」で高まる老朽原発の“放射能漏れ”リスクを専門家が警鐘
2022/11/04 06:00福島第一原発事故を機に制定された原発運転期間を原則40年・最長60年とするルール。そのわずか11年後の今、規制の撤廃が行われようとしているーー。「再生可能エネルギーと原子力はGX(グリーントランスフォーメーション)を進めるうえで不可欠だ」今年8月、GX実行会議で、電力不足への対応や脱炭素社会の実現にむけて原発の必要性をこう力説した岸田文雄首相(65)。会議で岸田首相は、次世代革新炉の開発・建設の推 -

“浸水リスク地域”の人口が急増ーーその背景にあるものは?
2022/06/23 06:00大雨やゲリラ豪雨が懸念される季節がやってきた。地球温暖化の影響か、豪雨や洪水などの水害が近年相次いでいる。そんななか、NHKの報道が注目を集めている。『NHKスペシャル』(6月5日放送)と、NHKが運営するNEWS WEB(6月3日公開)で、浸水のリスクが高い地域の人口が急増していることが報じられたのだ。NHKは明治大学の野澤千絵教授と東洋大学の大澤昭彦准教授と共同で調査を実施。浸水時に深さ3%以 -

防災専門家が推奨「水害のときに命を分ける『2つの荷物』作り方」
2022/06/23 06:00大雨やゲリラ豪雨が懸念される季節がやってきた。地球温暖化の影響か、豪雨や洪水などの水害が近年相次いでいる。はたして、どのように備えるべきか。「家を購入する際は各自治体で公表しているハザードマップなどを見て検討すべきです」そう語るのは、YouTube「そなえるTV」を運営する、備え・防災アドバイザーの高荷智也さん。「地震の予知と違い、水害の被害予想はかなり正確です。これまでの『想定外の雨量』による被 -

矛盾だらけの小池都知事 修学旅行に中止要請も約40人のパラ歓迎会には出席
2021/08/25 11:00「それぞれのパートナーのトップが直接あいさつする場は今の社会の慣習においては適切な範囲内」こう語ったのは東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の高谷正哲(43)スポークスパーソン。各メディアによると、組織委は23日夜、国際パラリンピック委員会(IPC)のアンドリュー・パーソンズ会長や理事を招き、都内のホテルで非公開の”歓迎会”を実施。組織委の橋本聖子会長(56)が主催し、菅義偉首相(7 -

気付かぬうちに脱水に…油断が招く「室内での熱中症」危険エリア3
2021/08/21 15:50長引く猛暑で熱中症患者が後を絶たない。コロナ禍で在宅の時間がほとんど、という人も油断は禁物。気づかぬうちに体が危険と隣り合わせになっている恐れがあるのだーー。「急激に暑くなったうえに、コロナ禍で迎えた2度目の夏。これまで以上に熱中症になるリスクが高まっています」そう語るのは、熱中症に詳しい済生会横浜市東部病院・患者支援センター長の谷口英喜先生。「今年は梅雨入りが早く、汗をかいて体内の熱を発散する機 -

市販胃腸薬には認知症のリスク!薬剤師が教える常用避けたい薬
2021/08/20 06:00「『お薬を飲み続ける=病気が治る』ではありません。逆にずっと病気が治らないからお薬を飲み続けているのです。このことに気づかない限り、長期にわたって薬を飲み続けていると、その弊害として副作用の影響を受けることになります」こう話すのは、「薬を使わない薬剤師」として活動している宇多川久美子さんだ。「症状が体に出ているということは、『体の状態に異変がある』という体からのシグナルです。熱や発疹が出たり、鼻水 -

薬剤師が警鐘!飲み続けると危険な薬リスト 脳梗塞の原因にも…
2021/08/20 06:00健康のための薬だが、副作用はつきもの。怖いのは「依存」してしまった場合だ。医師や薬剤師の指示に従うことが第一ではあるものの、薬の別の側面も見てみようーー。「『お薬を飲み続ける=病気が治る』ではありません。逆にずっと病気が治らないからお薬を飲み続けているのです。このことに気づかない限り、長期にわたって薬を飲み続けていると、その弊害として副作用の影響を受けることになります」こう話すのは、「薬を使わない -

選手検査も不十分! 五輪強行で都内重症者500人増のリスク
2021/07/01 06:00〈無観客開催は、会場内の感染拡大リスクが最も低いので、望ましいと考える〉〈観客がいる中で深夜に及ぶ試合が行われていれば、営業時間短縮や夜間の外出自粛等を要請されている市民にとって、「矛盾したメッセージ」となります〉6月18日に、そんな文言が書かれた“提言”を発表したのは「コロナ専門家有志の会」だ。この提言の正式名称は「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う新型コロナウイルス感 -
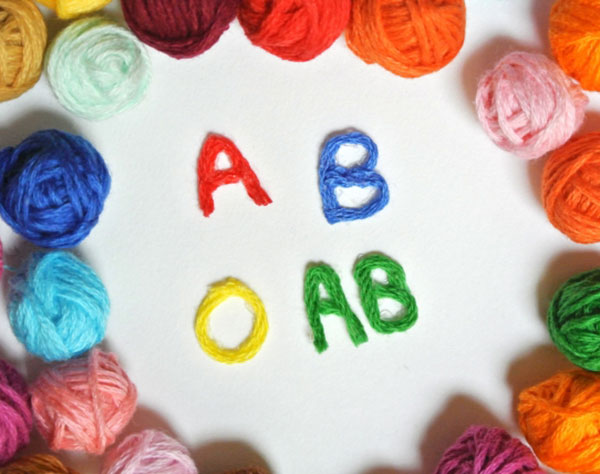
血液型でかかりやすい病気は違う…最新医学の統計から分析
2021/01/11 11:00緊急搬送された患者のデータなどから医学統計の専門家が分析。その結果わかった「血液型によってかかりやすい危険な病気」を知り、日常生活から予防の意識を高めようーー。日本では、血液型占いが盛んなため、身近な「ABO式血液型」だが、世界の医学者が血液型と病気の関係性について注目したのはつい最近のこと。「血液型というのは、医学的にはRh(+)(−)のほか、100種類以上の分類があります。そのなかでABO式は
