健康
1401 ~1425件/2460件
-

「歩幅広い人は認知症なりにくい」医師が語る“健脚”のカギ
2019/08/22 15:50健康な足でいつまでも元気に歩くため、基本となるのは、ふだんの正しい姿勢と歩き方だ。「たかが姿勢」と甘くみてはいけない。悪い姿勢は一日二日でできるのではなく、体のアンバランスや弱い箇所をカバーするために年月をかけて積み重なってできたもの。そして、その歪みが筋肉や関節の骨に負荷をかけたりすることで、肩こりや腰痛、関節痛を引き起こす原因となる。裏を返せば、正しい姿勢を維持することで、筋肉への負荷が軽減さ -

足の健康をおびやかす「変形性ひざ関節症」を見抜くサイン
2019/08/22 15:50“健康長寿”をかなえるために特に大切なのが丈夫な足腰。健脚を維持していくために、まずはいまの状態を客観的にチェックするところから始めよう!昨年の厚生労働省の発表によると、日本人女性の平均寿命は87.26歳、健康寿命は74.79歳だった。「健康寿命」とは、「健康上の問題がない状態で、日常生活が制限されることなく自立した生活ができる期間」のことを指す。すなわち、女性は人生の最後の約12年半、介護など周 -

転倒リスクは認知症リスクに“足の衰え”について知ろう
2019/08/22 11:00昨年の厚生労働省の発表によると、日本人女性の平均寿命は87.26歳、健康寿命は74.79歳だった。「健康寿命」とは、「健康上の問題がない状態で、日常生活が制限されることなく自立した生活ができる期間」のことを指す。すなわち、女性は人生の最後の約12年半、介護など周囲のサポートを必要としていることになる。この平均寿命と健康寿命の差が生まれる原因の多くは「運動器の障害」によるものだと、国立長寿医療研究セ -

内臓脂肪を蓄積させない!「おじさんの病気」を遠ざける8カ条
2019/08/16 11:00尿路結石、高尿酸血症……。なんとなく「男性しかかからない」と思っていた病気に悩まされる女性が増えているそう。実は、女性ならではの生活習慣が招くことも多い「気をつけるべき病気」を知り、病気を招く生活習慣を正しましょう。「冷や汗が出るほど激しい痛みが下腹部に走り、頻尿で何度も駅のトイレに駆け込んで用を足すと、便器が血で真っ赤になったので思わず叫んでしまいました——」悪夢の出来事を振り返るのは、都内に住 -

尿路結石、痛風、脂肪肝…「おじさんの病気」が女性に急増中!
2019/08/16 06:00「冷や汗が出るほど激しい痛みが下腹部に走り、頻尿で何度も駅のトイレに駆け込んで用を足すと、便器が血で真っ赤になったので思わず叫んでしまいました——」悪夢の出来事を振り返るのは、都内に住む50代の女性。病院に駆け込むと「尿路結石」と言われた。「尿路結石は汗を大量にかく夏場によく起こる病気です。体内の水分が汗で失われるので、尿中のシュウ酸カルシウムの量が増えて結晶化される。つまり“石”ができます。その -

運動習慣でアルツハイマー型認知症は40%もリスク減に
2019/08/14 11:00「日ごろから、バランスのいい食事や適度な運動をすることを心がけ、積極的に社会参加することなどは、認知症発症リスクを下げるために有効かもしれません。久山町研究を含むさまざまな疫学調査データから示されています」そう話すのは、九州大学大学院医学研究院教授で医学博士の二宮利治先生。“久山町研究”は、福岡市の北部に位置する糟屋郡久山町(人口約8,900人)の住民を対象に、'61年から長年継続している生活習慣 -

歯の健康と生きがいも大切!九大教授が教える「糖尿病」予防
2019/08/14 06:00「日ごろから、バランスのいい食事や適度な運動をすることを心がけ、積極的に社会参加することなどは、認知症発症リスクを下げるために有効かもしれません。久山町研究を含むさまざまな疫学調査データから示されています」そう話すのは、九州大学大学院医学研究院教授で医学博士の二宮利治先生。“久山町研究”は、福岡市の北部に位置する糟屋郡久山町(人口約8,900人)の住民を対象に、'61年から長年継続している生活習慣 -

九大教授伝授!認知症予防には一汁一菜で糖尿病にならないこと
2019/08/14 06:00治療が難しい認知症。正確な予防法をあぶりだすために、町の住民ほぼ全員の生活を長年追いかけた、画期的な調査がある。認知症発症の有無から見えてきたものとは——。「日ごろから、バランスのいい食事や適度な運動をすることを心がけ、積極的に社会参加することなどは、認知症発症リスクを下げるために有効かもしれません。久山町研究を含むさまざまな疫学調査データから示されています」そう話すのは、九州大学大学院医学研究院 -

胃がんはバリウムより胃カメラ、がんの早期発見で知るべきこと
2019/08/13 11:00今年1月に岐阜市で胃がんの検診を受けた50代の女性が、7月16日に亡くなった。「要精密検査」と診断されていたにもかかわらず、「異常認めず」と誤って通知されていたのだ。市区町村が実施するがん検診への信頼を、大きく揺るがす事件であった。「全国の自治体で行われているがん検診で、正しくがんが発見できる精度は、そもそも7〜8割。4〜5割の自治体すらあります。がんの見落としは、かなりの確率で起こりうるのです」 -
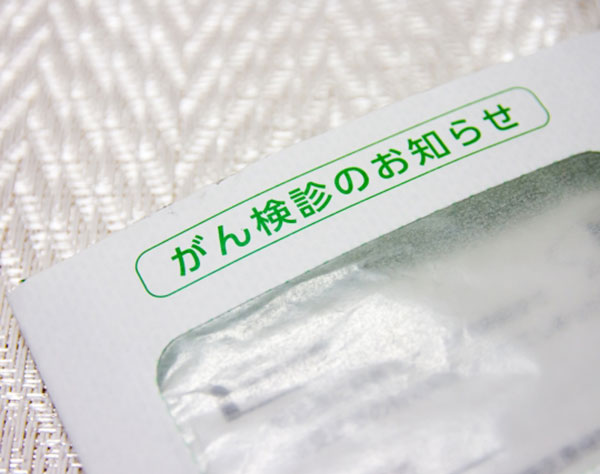
大腸がん、肺がん…検診ではわからない「見落とし」のリスク
2019/08/13 06:00今年1月に岐阜市で胃がんの検診を受けた50代の女性が、7月16日に亡くなった。「要精密検査」と診断されていたにもかかわらず、「異常認めず」と誤って通知されていたのだ。市区町村が実施するがん検診への信頼を、大きく揺るがす事件であった。「全国の自治体で行われているがん検診で、正しくがんが発見できる精度は、そもそも7〜8割。4〜5割の自治体すらあります。がんの見落としは、かなりの確率で起こりうるのです」 -

安くて安全にがんを消す放射線療法「コータック」が「日本ベンチャー学会会長賞」受賞
2019/08/03 15:50「今回の受賞で、安全・安価ですべての固形がん(塊を作るがん)に有効な『増感放射線療法・コータック』が世間に認知される可能性が広がることに、率直に喜んでおります」高知大学名誉教授で高知総合リハビリテーション病院院長の小川恭弘さんは、日本ベンチャー学会会長賞受賞決定の報を受けてこう語る。日本ベンチャー学会会長賞とは、文部科学省所管の国立研究開発法人「科学技術振興機構(JST)」と経済産業省所管の国立研 -

じつは“薬”が原因なのかも……その認知症“治るかもしれない”
2019/08/02 15:50近畿在住の70代女性は夫と死別して一人暮らしをしていたが、1年ほどしてから「夫が生きている」と口走って夜中に外を歩き回るようになったため、慌てた娘に連れられて精神科病院を受診した。この女性の診察にあたった、ひょうごこころの医療センターの小田陽彦認知症疾患医療センター長が、当時の状況を次のように話す。「お薬手帳を見ると、受診の1カ月前から『ベンゾジアゼピン受容体作動薬』という抗不安薬が投与されていま -

睡眠薬を使う前に変えるべき生活習慣、昼寝は15分までと医師
2019/08/01 15:50「人間は老化に伴い、メラトニンという“睡眠ホルモン”を産生できなくなってきますし、とくにリタイア後の高齢者は体を動かす習慣が減ります。ですから、現役時代と比べて高齢者が眠れなくなるのは“当たり前”と言っていいんです。しかし現在、睡眠薬に頼ろうとする高齢者が増え、彼らに睡眠薬を安易に処方してしまう医師がいるのです」こう語るのは、菅原脳神経外科クリニックの菅原道仁理事長。高齢の外来患者が睡眠不足を訴え -

副作用で事故のリスクも…高齢者に睡眠薬“ムダ処方”の実態
2019/08/01 15:50「5時間くらいしか眠れないのって、不眠症かしら?」。高齢親がそんな話を切り出してきたら“睡眠薬を飲むのはちょっと待って!”と声をかけてあげるべきかも。「人間は老化に伴い、メラトニンという“睡眠ホルモン”を産生できなくなってきますし、とくにリタイア後の高齢者は体を動かす習慣が減ります。ですから、現役時代と比べて高齢者が眠れなくなるのは“当たり前”と言っていいんです。しかし現在、睡眠薬に頼ろうとする高 -

にんにく、しょうがが“健康にいい”とされる真の理由とは
2019/07/25 06:00「女性の場合、大豆製品を種類多く摂取する人ほど、そうでない人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患のリスクが34%、全死亡リスクが14%低くなる――」今年3月、このような調査結果が国立がん研究センターから報告された。40~69歳の男女約8万人を20年近くにわたって追跡調査(コホート研究)したものだ。この研究を実施した大妻女子大学家政学部食物学科公衆栄養研究室の小林実夏教授は、研究内容について -

食材と疾患予防に因果関係、鍵は「抗酸化」と「抗炎症」に
2019/07/24 16:00「女性の場合、大豆製品を種類多く摂取する人ほど、そうでない人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患のリスクが34%、全死亡リスクが14%低くなる――」今年3月、このような調査結果が国立がん研究センターから報告された。40~69歳の男女約8万人を20年近くにわたって追跡調査(コホート研究)したものだ。この研究を実施した大妻女子大学家政学部食物学科公衆栄養研究室の小林実夏教授は、研究内容について -

死亡リスク高い病気予防に摂りたい食材、その科学的根拠
2019/07/24 16:00「女性の場合、大豆製品を種類多く摂取する人ほど、そうでない人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患のリスクが34%、全死亡リスクが14%低くなる――」今年3月、このような調査結果が国立がん研究センターから報告された。40~69歳の男女約8万人を20年近くにわたって追跡調査(コホート研究)したものだ。この研究を実施した大妻女子大学家政学部食物学科公衆栄養研究室の小林実夏教授は、研究内容について -

がん研究センターが報告「大豆製品で死亡リスク低下」の全容
2019/07/24 11:00「女性の場合、大豆製品を種類多く摂取する人ほど、そうでない人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞といった循環器疾患のリスクが34%、全死亡リスクが14%低くなる――」今年3月、このような調査結果が国立がん研究センターから報告された。40~69歳の男女約8万人を20年近くにわたって追跡調査(コホート研究)したものだ。この研究を実施した大妻女子大学家政学部食物学科公衆栄養研究室の小林実夏教授は、研究内容について -

血糖値気になる人に…鎌田實先生すすめる「かかと落とし」
2019/07/18 11:00「3年前に不整脈が出たときがきっかけで、『これはまずい、しっかり体を鍛えなくては』と危機感を覚えたんです」こう話すのは、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さん(71)だ。当時から地元での医療活動のほか、1年のうち100日間は全国のあちこちを飛び回って、精力的に講演活動をする日々を送っていたという。「15年くらい前から、行く先々で僕のオリジナルの『スクワット』と『かかと落とし』をすすめていたのですが、実の -

鎌田實先生がたどり着いた究極のスクワット法で若返り!
2019/07/18 06:00おなじみ鎌田先生、スリムになってます。実は自身で考案したエクササイズが功を奏したそう。若返り効果もあるとかで、人生100年時代を最後まで元気に生きるために、さあ、試してみよう――!「3年前に不整脈が出たときがきっかけで、『これはまずい、しっかり体を鍛えなくては』と危機感を覚えたんです」こう話すのは、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さん(71)だ。当時から地元での医療活動のほか、1年のうち100日間は全 -

鎌田實先生が71歳が3年間で9kg減、独自メソッドを公開
2019/07/17 11:00「3年前に不整脈が出たときがきっかけで、『これはまずい、しっかり体を鍛えなくては』と危機感を覚えたんです」こう話すのは、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さん(71)だ。当時から地元での医療活動のほか、1年のうち100日間は全国のあちこちを飛び回って、精力的に講演活動をする日々を送っていたという。「15年くらい前から、行く先々で僕のオリジナルの『スクワット』と『かかと落とし』をすすめていたのですが、実の -

便通促進、括約筋強化に!「腸ストレッチ」実践マニュアル
2019/07/12 11:00夏は室内と屋外の気温差や水分の取りすぎなど、体に負担をかけてしまいがちな季節。特に、腸へのダメージにご用心! そのコンディションは、健康寿命と大いに関係している――。「腸内環境を整えて健康を維持する“腸活”がブームですが、『腸にいい』と思っていた習慣が、じつは腸の状態を不調にする原因だった、ということがよくあります。腸が健康でないと、肌荒れなど見た目に影響が出るだけでなく、精神的にもストレスがたま -

「美腸エクササイズ」で便秘と下痢を抑え、強い腸を作ろう
2019/07/11 16:00夏は室内と屋外の気温差や水分の取りすぎなど、体に負担をかけてしまいがちな季節。特に、腸へのダメージにご用心! そのコンディションは、健康寿命と大いに関係している――。「腸内環境を整えて健康を維持する“腸活”がブームですが、『腸にいい』と思っていた習慣が、じつは腸の状態を不調にする原因だった、ということがよくあります。腸が健康でないと、肌荒れなど見た目に影響が出るだけでなく、精神的にもストレスがたま -

睡眠3時間まえに食事はNO!“腸にやさしい”24時間生活習慣
2019/07/11 11:00夏は室内と屋外の気温差や水分の取りすぎなど、体に負担をかけてしまいがちな季節。特に、腸へのダメージにご用心! そのコンディションは、健康寿命と大いに関係している――。「腸内環境を整えて健康を維持する“腸活”がブームですが、『腸にいい』と思っていた習慣が、じつは腸の状態を不調にする原因だった、ということがよくあります。腸が健康でないと、肌荒れなど見た目に影響が出るだけでなく、精神的にもストレスがたま -

夏場は「腸トラブル」がいっぱい!「1日終わりに湯船」で対策
2019/07/11 06:00「体の冷えは、内臓の血流を滞らせ、腸の動きを悪化させてしまいます。特に更年期以降の女性は女性ホルモンバランスの乱れや加齢に伴う筋力の衰えにより、冷え性から慢性的な便秘を招きやすいので気をつけましょう」そう話すのは松生クリニックの松生恒夫院長。松生院長はこれまで4万件以上の大腸内視鏡検査を行い、“汚腸”の人を救ってきた便秘外来のスペシャリストだ。便秘は腸の老化を早めるだけでなく、万病のもと。便秘が長

